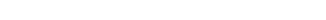インタビュー
オールインクルーシブな社会を諦めない。 多様性を受け入れる服のつくりかた
Date: 2022.02.10 THU
#ソーシャル
#新規事業
ダイバーシティ、インクルーシブという言葉を目にする機会が増えた近年、いろいろなことに配慮した製品やサービスが多く生まれています。
今回お話を伺った田中美咲さんが運営するSOLIT!では、さまざまな体型や障がいのある人でも自分から選んで着たいと思えるような服づくりを行っています。
田中さんが目指すのは、単にファッションブランドをつくることではなく、「オールインクルーシブな経済圏」を実現すること。オールインクルーシブ(All Inclusive)は直訳すると「全てが含まれる」という意味の言葉。それぞれが違いをありのままに受け入れ、健全に共存できる社会の実現を野望として掲げています。
今回のインタビューでは、SOLIT!の活動について、また多様な人と関わりながら事業を行っていくなかで考えていることを田中さんに伺いました。
課題があるなら、解決しないと
――「SOLIT!」を立ち上げる前、田中さんはどのような活動をされてきたんですか。
学生時代は、バックパッカーで世界中を旅しながら、各地の社会課題を実際に見にいくような生活を送っていました。世界にはいろいろな生活環境があることを目の当たりにして「多くの人を一同に幸せにする機会ってどうやってつくるんだろう」と考えるようになったんです。
大学卒業後、一度企業に就職したものの、入社して1年で東日本大震災があったことをきっかけに、会社を辞めて福島県の復興支援事業の責任者になりました。そこで感じたのは、政府や自治体が考える復興と、地元の人達たちの感情にギャップがあること。復興を、と支援する側はどんどん進んでいくけれど、それを受け取る方々のなかには家族が亡くなったことを受け入れるのに時間が必要な方もたくさんいらっしゃって。平和な社会にしたいのはみんな同じだけど、支援する側のスピードと受け取る側の意向が全然違うことを実感しました。
だからこそ、政府や自治体の指針に沿って支援を進めるのではなく、もっと今現場が必要とすることに集中したい。そういう思いで、「防災ガール」という一般社団法人を立ち上げ、より自由に支援内容を決めることができる立場で支援をすることを選びました。復興支援ではなく、次の災害の被害を最小限にする防災や、防災そのものの定義をアップデートすることを思想として、2020年まで活動を続けてきました。
――防災について考えてきた田中さんが、ファッションの分野で活動を始めたきっかけはどのようなものだったのでしょうか。
一般社団法人防災ガールを解散後、社会課題解決に取り組む団体・企業の後方支援をするmorning after cutting my hair,Inc.という会社を立ち上げました。さまざまな団体・企業を支援していく上で、当時の自分の知識領域では社会課題の周知啓発はできたとしても、本来行うべき社会課題解決にまで踏み込めていないということを感じていて、大学院に通い、学び直しをすることにしました。そこの同級生に元車椅子バスケの選手がいたんですね。彼は服をとてもおしゃれに着こなしているように見えたけれど、身体の可動域や麻痺によって硬い生地の服やボタンやチャックのある服が着づらく、セーターやパーカーなど上から被る着衣方法の服ばかりを選択していると聞きました。特にフォーマルな場面では、周りと同じように細身のジャケットやボタンシャツ・ネクタイを着たいけれど着るのには時間がかかったり、サポートが必要だという悩みを聞きました。
それから私自身の原体験からいくと、小さいころから水泳やバスケをしてきたので、太ももが大きかったりするんです。だからショッピングモールに入っているブランドで服を選ぼうとすると、自分の体型に合ったものがなかったりするんですよ。似合う服がないのは、私が細くないから駄目なんだって自分に言い聞かせてきました。ファッションで幸せになるという経験は、ほとんどしたことがありませんでした。
私は体型によって着るものに課題を持っていたし、彼は障がいで着るものに選択肢が少なかった。こうして課題を持っている人がいるんだったら、何かしら解決しないと、と思ったんです。
ファッションは、世界中の人が必ず毎日触れるものですよね。一番身近なものから意識変革のための設計をしたかったので、この分野に取り組むことにしました。それに加えて、ファッション業界は生産から廃棄に至るまで、全ての工程で課題があると思っていて。環境負荷だったり人権侵害だったり、さまざまな社会課題とつながっているんです。
いつまでも完璧にはならない服づくり
――SOLIT!ではさまざまな体型や障がいのある方が選んで着られる服をつくっていらっしゃいますよね。服づくりは、どのように進んでいったのでしょうか。
まずは服に課題を感じている友人たちに話を聞かせてもらいました。そうしたら、セットアップのようなフォーマルなものを着たいけど、体の麻痺などによって指が動きにくくボタンが留められないとか、腕が回りにくくて着られないという声が多かったんです。だったらフォーマルにもカジュアルにも使えるセットアップやシャツを一度つくってみようということになって。
既存の服を購入して、脊髄損傷だったり脳性麻痺だったり、いろいろな障がいのある方に着てもらいながら、どこが着づらいのか、動きにくいのかをチェックしていきました。何度も微調整を続けながら、ようやくリリースすることができたのが今の製品です。ただ、今でも誰にでも着られると言えるところにはまだ至っていなくて。いつまでたっても完璧にはならないという前提で、日々アップデートを続けています。
現在は12サイズを用意。セミオーダーで袖口、ボタン、裾など各パーツを選ぶことが可能。
生地には伸びがよく着脱しやすいジャージー素材や、ハリがあり家庭でも洗濯しやすいさまざまな素材をラインナップ。
――現在の製品ができるまでに、特に工夫したポイントがあれば教えてください。
私も話を聞いていくなかで知ったんですが、車椅子ユーザーの方って、自走するのに、車輪に裾が当たって汚れるんです。だからほとんど必ず腕まくりをするんですね。私たちの製品は袖口にゴムを入れていたり、リブを挟んで腕まくりをしても落ちないような構造にしています。
SOLIT!の試着会で、人生で初めてジャケットを着ることができたという方も少なくありません。ジャケットを着ることによってちょっとおしゃれなバーに行けるようになったり、ジャージでは行けないホテルのレストランを予約することができたり。服一つで社会参加が促されたというか、その人の人生が変わっていく。その人の世界や人生の選択肢がぐっと広がるのは、すごく嬉しいですよね。
勝手にニーズを想像しない
――ターゲットを絞らず、広くいろいろな人の意見を取り入れながら商品をつくっていくことに難しさはありませんか。
ターゲットやペルソナを決めるというのは、企画者から見るその人の思想を勝手に決めているだけだと思っていて。同じ車椅子ユーザーがいても、考え方も性格もぜんぜん違いますよね。要素として同じものはあるかもしれないけれど、基本は全員、みんな違う人だという前提に立っています。
勝手に想像しない、というのは大切にしていることの一つですね。障がい者やセクシャルマイノリティなど、身近にいない人は、自分とはまったく違う世界の人として捉えてしまう人が少なくないんです。だけどいざ話してみると、利用している制度やシステムが違うだけで、例えば趣味が同じだったりする。ほとんど何も変わらないんですよ。
最近は企業でダイバーシティやインクルージョンを推進するチームができて、勝手に「LGBTQの人はもっと生きやすい方がいいんだ」と仮説を立てて動いていたりしますよね。実際に当事者に話を聞いてみると、別にそんなことないよってこともたくさんあって。求めていることは個人個人で違うんです。勝手に決めつけない、勝手に想像しないっていうことは、これからも大事にしていきたいですね。
――個人個人に向き合っていく。SOLIT!ではどのように、声を集めているんですか。
私たちは病院と連携しながら、それぞれの障がいや身体の可動域、心理状況に合わせて、どんな服が着れるのか、着たいのかを臨床の患者さんごとに聞いています。例えば心理的なことでいうと、戦地に行ったことのある人にとって、茶色や緑の服に怖さを感じたり、血液に近い色を見ると不安になるということがあったりする。そんな方々でも自分で選んで、気持ちよく着られる服をつくれる方がいいですよね。最近だと、ボタンをマグネットにすることで着脱にかかる秒数がどれだけ減るのかをカウントしていて。秒数が減るということは着やすくなる、その服を選びやすくなるということだと思うんです。
どのパーツを変えるとよりQOL(Quality Of Life)が上がるのか、満足度が上がるのかということを、パーツごとに定性的な調査をしていくんです。そこに合わせて、普段の生活環境でどのようなことに困っていて、それが解決できるとより豊かになるのか、定性的に調査を並行して行っています。
ボタンを留めることが難しい方に向けたマグネットで取り外しできるボタン。見た目からは気づかれにくい、選択肢を広げるこだわりがある。
――ここで、現場でのニーズをヒヤリング、データ化していく役割を担っている伊藤さんにもお話を伺います。地道に調査をしていくなかで、どのような工夫をされているか教えてください。
プロジェクトマネージャーの伊藤由紀子さん。臨床現場におけるユーザーからのヒアリングなどを主に担当。
私は普段、鍼灸師として働いています。臨床の現場では目の前の患者さんから直接話を伺い、治療法を提案しています。患者さんの状態に100%で向き合い、そこに優劣もなければ正解不正解もありません。けれどSOLIT!で製品にしていくためには、より広く考える必要があって。ヒヤリングしていくといろいろな声を聞かせていただくので、どこまでのニーズを製品に取り入れるのか、どのくらいの人を包括した製品にするのかは、チームのメンバーと頭を抱えたところでした。
議論を重ねるなかで、この服は身体の動きや身体機能を持っている方に着ていただけるのかを整理するマップをつくりました。そのとき、一気に視点が変わったんです。いつもまっすぐ患者さんを見ていたのを、俯瞰して考えられるようになりました。
――さまざまな課題に対して、どう解決していけるかを可視化していったんですね。
はい。マグネットボタンだったらこういう課題を持つ人たちは包括できるけど、スナップボタンだったらこのニーズには応えられない、というようなことをチェックしていきながら、落とし所を決めていきました。
試着会では、できたものを実際に着ている人を前に、今のカスタマイズだと解決できない課題を知ることもあります。一つ一つに答えたいけれど、全ては難しいという悔しさはありますね。まだまだ網羅できないことがあると分かって、来月(2021年12月)にはサイズ展開の追加も控えています。できることから少しずつ、変えていけたらと思っています。
オールインクルーシブな経済圏をつくる
――改めて田中さんに伺います。SOLIT!が動き出した今、これから取り組んでいきたいと考えていることはありますか。
SOLIT!はできる限り多くの人を包括していく服づくりをしているので、例えばゴスロリとかサーフ系とか、個性の出るファッションを求める人には物足りない部分があるかもしれません。その代わりに、既にあるブランドに私たちの知見やノウハウをお渡しして、各ブランドの中でインクルーシブなラインをつくっていくことはできます。そのブランドを買いたいけど買えない人がいる。私たちだけで新しいものをつくっていくよりも、すでに課題を持っているところを解決していく方が、助かる人が増えると考えています。
今はファッションからスタートしていますが、臨床の現場から集めたデータを使って、医療福祉や自動車、建築、文具や家具など、まだインクルーシブな状況になっていない分野を変えていく支援もしていきたいと思っています。生活必需品である衣食住に関わることを、早く変えていきたいですね。
最近色々な方の話を聞いて感じるのは、ダイバーシティ&インクルージョンを推し進めようと企業が考えるときに、社内のことばかりに目が向いてしまい、社会に目を向けていないこと。本来は、自社の事業を通じて、社会に向けたダイバーシティ&インクルージョンの設計と実践が必要だと思うんです。だから、その実践をもっとサポートしていきたい。いろいろな分野の人と連携しながら、一緒にできることを探っていきたいです。
着心地・サイズを体感してもらうための試着会も毎月開催。試着会もユーザーの課題を発見する機会となっている。
――大阪の岸和田にある病院と連携して、病院服づくりなども始まっていると伺いました。
はい。その病院に勤めている方がSOLIT!のTwitterを見つけてくださったことがきっかけで、患者さんにヒアリングさせていただいて、病院服をつくっています。服が壊れたら地元のリペア屋さんと連携して直してもらったり、廃棄せざるを得ないときには自治体や産業廃棄物処理場の方と連携しながら、地域で循環していける服をつくろうとしています。
――いろいろな分野の方を巻き込みながらプロジェクトを進めているんですね。
SOLIT!はいわゆるソーシャルビジネス、社会の課題解決のために立ち上がりました。自分たちで利益をたくさん出していくことを目指してはいないんですよね。大きな目標は「オールインクルーシブな社会」の実現です。SOLIT!をきっかけに出会って連携する企業が出てくるとか、建築だったり金融だったり、いろいろな分野でインクルードする事業が生まれて経済圏をつくることによって、生きやすい世の中ができていく。そのなかで自然とSOLIT!のことを認めてくれる人が増えていけばいい。みんなでやっていくからこそ、結果として大きなインパクトをつくることができますよね。
――オールインクルーシブな社会を実現する。そのためには個人だけでなく、いわゆる大企業、中小企業が意識変革していくことも必要になりそうですね。
そうですね。企業が変わらないと、社会は変わっていかないと思います。「CSR的にはこんな社会貢献をしています」と報告書に書いていても、本業のビジネスにおいて環境破壊に通じることをしてしまうということもまだまだあると思います。今は社内向けにサステナブルを意識した取り組みを始めているところが多いのかもしれませんが、その会社の事業自体が社会のダイバーシティ&インクルージョンやサステナビリティに寄与するものになっていかないといけないと思っています。
サステナビリティを掲げたとき、ものごとは100年単位で変わっていくため短期的なメリットは見込めないので、事業として取り組みづらいことは分かります。けれどサステナビリティやダイバーシティー&インクルージョンについては、企業がこれまでどれだけマイナスの影響を及ぼしてきたのかを理解する必要があると思うんです。企業が社会課題に取り組むことで、社会が変わっていく大きな力になる。事業の傍らで行う社会貢献ではなくて、本業の事業として、きちんと儲けながら社会課題の解決もできるサービスをつくっていくのが、企業の責任だと考えています。
まずは小さく実践しながら、一緒に取り組む仲間を見つけていく
――企業のなかには、その点に課題意識を持っている担当者の方も多くいらっしゃると思います。動き出す第一歩として、どのようなことから始めるとよいでしょうか。
まずはパートナーや協力者、仲間をつくることが重要だと思います。社内で一人で考えるのではなく、人に話すことで動き出す物事はたくさんありますよね。私の場合はTwitterで仲間が増えてきていて。服づくりのためのデザイナーが必要です、縫製する人が必要ですというときに、知り合いから価値観に共感してくださる方を紹介してもらうこともありました。今SOLIT!は社員1人、業務委託が2人、あとは40名ほどのプロボノが集まる組織になっています。個人として考えていることを言葉にして表に出すことで、いい出会いにつながっていると感じています。
また、私が何かを始めるときには、高速で仮説検証しまくるということを決めていて。多くの企業は企画書をちゃんとつくって、上長に提案して予算を取って、という流れがよくあると思うんです。そんな時間があるんだったら、まず自分一人でも試してみる。失敗したら別の方向を試す。そうやって成功確率を増やしていく方が、結果的に成功につながっていくと思うんですよね。
意思決定者の共感が得られず物事が止まってしまうときには、一緒に現場に行くことも重要です。例えば気候変動のことも日本にいると実感しにくいけれど、水害の多い国に行って状況を見ることで、自分たちがやってきたことが誰かを傷つけていたことに気づくことができる。現実を知った瞬間に意思決定が変わる場面に何度も立ち会ってきました。
あとはその分野で活動するアクティビストなど、斜めの関係から伝えてもらうことが分かりやすい刺激になることもあります。ダイバーシティ&インクルージョンなど、何か挑戦したいけれどパートナーが見つからないという方がいれば、ぜひご一緒できたら嬉しいです。
Interview
田中美咲 MISAKI TANAKA
奈良県奈良市出身。立命館大学卒業後、サイバーエージェントに入社。東日本大震災をきっかけに、2013年「一般社団法人防災ガール」を設立。その後企画やPRを担う「morning after cutting my hair,Inc.」、ファッションブランド「SOLIT!」を立ち上げ、社会課題の解決に取り組む。