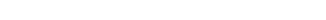解説記事
ニューロダイバーシティ 高度・先端IT人材獲得の新戦略
Date: 2025.05.13 TUE
#ソーシャル
#ESG投資・開示
前回記事では、脳・神経の発達の違いを社会全体として活かそうという考えである「ニューロダイバーシティ」を紹介しました。そして人口の1割程度とされる発達障がいがある人が、高度・先端IT領域において活躍する可能性を示しました。
例えば、自閉スペクトラム症の人がもつ高い集中力を活かし、データ分析やAI開発の分野で活躍する例などが出てきています。
本稿では、ニューロダイバーシティをどのように企業の競争力につなげていくべきかについて具体例を交えてお伝えします。
不足する高度・先端IT人材
まず、高度・先端IT人材の獲得がいかに難しいかを見てみます。
日本では人口減少が進む中、2040年には1,100万人の労働力不足が予測されています。推計人口は1億1,092万人で、実に人口の10%程度の労働力が不足することになります。
出典:リクルートワークス研究所 「未来予測2040 労働供給制約社会がやってくる」 (2023年03月28日発行)
デジタル領域についても傾向は同様です。経済産業省の調査[*1]によると2030年に45万人のIT人材の需給ギャップが発生すると予測されており、不足するとされているのはすべて先端IT人材です。
そして、下図の通り、現時点ですでに人材の質・量共に不足感が高まっています。
こうした状況の下、各企業は社内人材を高度・先端IT人材にするべく育成に力を入れています。経験者採用も行っているものの、人材市場における供給が需要に追いついていないことから、社内人材の育成にシフトしつつあると思われます。
一方で、働く人から見ると、「学び直しのための時間確保」がハードルになっているという調査結果もあります。多忙な人々の学び直しを後押しするためには各企業内で現業との時間配分の調整などが必要です。そのためには、企業内での合意形成とそのための明確な人材育成戦略が求められ、成果が出るまでには相応に時間がかかると考えられます。
並行して、報酬等の魅力的な処遇の準備が人材確保・獲得の正攻法となりますが、獲得競争が激化していく中では消耗戦となるのは時間の問題と考えられます。
ただ、これらの高度・先端IT人材の獲得の難しさは、既存の人材市場における経験者採用や社内人材育成を想定すれば、という話です。まだ企業が十分な接点をもっていない人材に目を向けるとどうでしょうか。すなわち発達障がいがある人たちです。発達障がいがある人たちは大卒全体と比較し就職率が30ポイント近くも低い状況に置かれており、労働力としてのポテンシャルはかなり大きいと考えられます。
活躍事例は前回記事をご覧頂くとして、本稿では高度・先端IT人材に必要とされるスキルに着目します。スキル要素を定義した「デジタルスキル標準」を見ると、実は一般的な発達特性との相性が良い要素が多く見られます。
例えば、データを扱い、判断する力や反復的なアプローチは自閉スペクトラム症(ASD)の発達特性との相性が良いと考えられます。
また社会の変化を捉える力や変化への適応、常識にとらわれない発想は注意欠陥・多動症(ADHD)の発達特性が活きる可能性があります。
発達障がい者の能力発揮に向けたマネジメントへ
これはあくまで一般論ですので、さらに踏み込んで、日本総研が主催しているニューロダイバーシティマネジメント研究会の検討結果を紹介します。研究会では、発達特性との相性が良いと考えられる高度・先端IT業務を特定し、発達障がいがある人たちが能力を発揮しやすい職場環境づくり(マネジメント手法)に向けた検討を参加企業とともに行っています。
参加企業の実務を対象に、発達障がいがある人の能力発揮を阻害しうる要素がどの程度含まれるか、また業務や環境がどの程度の柔軟性をもっているかという観点で、業務の分析と再設計を行いました。実務の内容は開発中・運用中のITシステムに対する技術的診断です。
意外に感じる方もいるかもしれませんが、ある企業の現状の業務に関しては、発達障がいがある人の能力発揮において「大きな懸念は無い」という結果が得られました。これには業務の2つの特徴が関わっていました。
1つ目は、正確性と論理的思考力が求められる業務であることです。これは特にASD特性がある人の能力発揮が見込みやすい内容です。
2つ目は、発達特性として、苦手であることが多い「調整・交渉」が含まれていないことです。この業務では「調整・交渉」をリーダーが担っていました。
また、別企業の類似の実務では「調整・交渉」が含まれていましたが、その部分をほかの人と分担する再設計を日本総研から提案しました。その結果、能力発揮を阻害しうる要素を現状の35%から6%まで削減できました。残る6%も、主担当ではない会議をリモート参加できるようにするなどで削減しうる内容です。再設計案は現場マネージャーの感覚とも非常に近く、大きな負担はなく実施できそうという反応を得られました。
業務再設計のポイントは、「技術的な専門性を磨いていく役割」と「社内外で調整・交渉する役割」を分けることです。両方ともできる人材はそもそも非常に希少ですから、人材へのリーチという面でも合理的でしょう。そして2社ともから採用も前向きに検討したいというフィードバックがありました。これは、実際に人材獲得の難しさを痛感しているマネージャーの声であり、高度・先端IT人材の獲得戦略としての可能性が示唆されたと考えています。
このように発達障がいがある人の能力発揮を徹底して考えることで、高度・先端IT人材獲得の新戦略としての可能性が見えてきました。
一方で、発達障がいがある人は即応的な会話が苦手だったり、社会的な文脈の理解が得意ではなかったりするため、面接重視のプロセスではこうした人材とのマッチングが難しい面があります。専門性や得意なことを見極めるため、たとえばインターンシップで具体的な課題を設定し、成果や技術力の評価を行うなどの手法が考えられます。
研究会では2025年度にニューロダイバーシティを前提としたインターンシッププログラムを企画し、高度・先端IT人材獲得の新戦略として機能しうるか検証したいと考えています。
発達障がいがある人にはもっと挑戦したい、活躍したいという人がいます。人材不足の解消と共に、発達障がいがある人の挑戦したい・活躍したいという思いが叶う就労機会を創出し、その先に障がいの有無に関係なく存分に能力が発揮できる社会を目指していきたいと思います。
*1 経済産業省 IT人材需給に関する調査(概要) 2019年4月