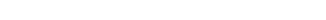インタビュー
全ての人が対等に、快適に働ける場をつくる——日揮パラレルテクノロジーズ
Date: 2025.08.25 MON
#ソーシャル
#ESG投資・開示
左から、取締役副社長CTOの長尾浩志氏、キャリアデベロップメントマネージャー(CDM)の瀬野尾安弥子氏、代表取締役の阿渡健太氏、執行役員COOの關健宏氏
GGP Edge Programとは?
| GGP Edge Program(以下Edge Program)は、本業を通じて社会的価値を創出する企業や事業をSMBCグループが支援するプログラムです。2024年度は7月より支援先を公募し、11月の選考会(詳しくはこちら)を経て3社を選出しました。 選出企業には、Edge Programとして、日本総合研究所(以下日本総研)の有識者によるメンタリングを3回、アントレプレナーシップや経営戦略を専門とする京都大学の山田仁一郎教授によるメンタリングを2回行いました。 本記事では、Edge Programに参加した各社の皆さまにプログラムの手応えを伺い、3回シリーズでレポートします。 |
参加企業:日揮パラレルテクノロジーズ
| 「障害の有無に関わらず、すべての人が対等に働ける社会の実現を目指す」。そうミッションに掲げる日揮パラレルテクノロジーズ(横浜市/以下JPT)は、日揮ホールディングスの特例子会社として2021年に設立されました。 2025年8月現在、社員数は45人、設立4年で社員が7倍に増えた成長中の企業です。一般的な特例子会社の1.75倍となる、350万円の年収を実現しています。 フルリモート、フルフレックスを導入し、1人1人のスキルや環境に丁寧に向き合いながら新時代の働き方モデルを構築することを目指しています。 Edge Programの選考会では、多様な雇用のあり方にチャレンジし、実績を上げていることが高く評価されました。そのようなJPTの事業が社会に与えるインパクトとは——? JPTの経営を担う代表取締役の阿渡健太氏、取締役副社長CTOの長尾浩志氏、執行役員COOの關健宏氏、キャリアデベロップメントマネージャー(CDM)の瀬野尾安弥子氏の4名にお話を伺いました。 |
IT×障害者雇用でニューロダイバース人材を活かす
——JPTを設立した背景を教えてください。
代表取締役の阿渡健太氏
阿渡 僕が日揮ホールディングスの人事担当をしていた頃、日揮グループ内の障害者雇用を円滑化するために特例会社を作ることになりました。でも、会社を作るといってもいったい何をすればよいのかと、前社長の成川潤と2人で頭を悩ませていました。そんな中、IT分野に特化した就労移行支援事業所を見学にいくと、自閉スペクトラム症やADHDなどの発達障害をもつ人たちが高い集中力や論理的思考力を活かし、AIやWeb制作などの分野で実力を発揮していました。いわゆるニューロダイバース人材です。
かつ日揮の中ではDX促進が必要だったので、「IT×障害者雇用」という良い掛け算ができると考え、IT人材をメインとしたJPTを設立しました。
僕自身、生まれつきの障害当事者です。「働けない」という偏見にさらされてきた経験があります。そういう社会を認めたくないという思いがありました。我々の取り組みを広く知ってもらい、どんどん社会に浸透させたいという思いでEdge Programに応募しました。
——経営陣の皆さんは、IT×障害者雇用という掛け算の中で、それぞれどのような役割を担っているのでしょうか?
取締役副社長CTOの長尾浩志氏
長尾 僕は2023年4月に日揮グローバルから出向してきました。日揮グローバルではプラント設計をしていて、AIを使った自動化などDXの必要性を感じていました。そうした時にJPTが立ち上がり、一緒に仕事をしてみると、本当にスキルの高い人材が揃っていることを実感しました。
日揮グローバル内で個別にDXを進めていくよりも、JPTを強化した方が結果として本社のDXに貢献できると考え、出向を決めました。
JPT内では最高技術責任者(2025年3月時点)として、仕事を受注しプロジェクトの進行管理や質の向上に尽力しています。
執行役員COOの關健宏氏
關 僕は日揮グローバルの土木系のプラントエンジニアとして、中東や東南アジアへの長期出張を繰り返していました。しかし、子供ができて半年間の育休をとったことをきっかけに、育児と仕事を両立できる方法を模索し始めました。ちょうどその頃、同期入社の長尾さんからJPTに誘われ、働き方を変えてみる良い機会だと思い出向を決めました。
今は事業部長(2025年3月時点)という立場で、顧客とエンジニアの間を調整し、成果を上げる責任を負っています。
キャリアデベロップメントマネージャーの瀬野尾安弥子氏
瀬野尾 JPTに入社する前、私は障害者の就職支援をしていました。そこでは、障害者は職種も限られ、給与も低いという現実に違和感をもっていました。求職者の中には、もともとバリバリと仕事をしていたけれど、精神疾患などで離職した人が多くいました。職歴もスキルも高い人が、一旦離職すると出口がないことにジレンマがありました。
JPTは障害者のスキルを活かすという考え方で、そこに魅力を感じて転職しました。
——JPTは障害者雇用の枠を超えた、新しい働き方を提案しています。
阿渡 JPTの就業規則は、他社にはないユニークなものです。一般的に大企業では病気などで休職できる手厚い補償があります。日揮ホールディングスの場合は数年単位と手厚いです。しかし、それが障害者雇用のリスクになってしまうのです。JPTでは手厚い補償をやめて、「No Work, No Pay. Pay for Value」を徹底しています。また、通勤して9時から18時まで同じ場所で働く必要はないという考えで、フルリモート・フルフレックスを導入。これが今のところ上手く機能し、自己都合退職者はいません(2025年3月時点)。
この就業規則は、障害者雇用に限らず、例えば育児や介護などをしている方にも適用できます。みんなが対等に働くことができる社会を目標にしています。
社外新規事業×先端AIサービス提供で社会にインパクトを
——Edge Programでは、日本総研と共にロジックモデルを作成していただきました。これらの経験を経て、何か変化はあったでしょうか?
阿渡 日本総研によるメンタリングでは、最初に我々から提出したロジックモデルのスケールが大きすぎるという指摘を頂きました。そこで、まず、ステークホルダーの変化に着目して話を始めることになりました。
Edge Program 応募時のロジックモデルを日本総研が整理した初期段階のロジックモデル 図作成:日本総合研究所
阿渡 さらに、会社全体ではなく、僕たちが今手掛けようとしている社外事業について解像度を上げてロジックモデルを作成しました。この事業はJPT との親和性が高いと考えており、そこから我々の事業が社会に与えるインパクトを考えたロジックモデルです。かなり詳しく、大きな図になったので、さらに短期・中期・長期に分け焦点を絞ることも試みました。
ある社外事業のロジックモデル 図作成:日本総合研究所
長尾 この案件では先端AI等を活用したシステム開発を行います。
僕自身、だれもが対等に働ける社会という当社のミッションと、先端AI等を使った本事業の関連性をあまり意識できていませんでした。でもロジックモデルを整理し、中期・長期のアウトカムを考える中で、この事業が社内外に及ぼす影響を考えるようになりました。この事業をやり切った先にどのようなインパクトがあるのか、皆で議論ができました。
阿渡 その議論を通して、僕自身がパラテコンドーのアスリートとして活動していることが事業の推進にも活かせるのではないか、という期待感が得られました。それはとてもワクワクすることです。
關 JPTがテクノロジーを活用して本事業を推進できたら、技術力だけでなく、我々の働き方や人にも注目が集まると思います。それはJPTらしい仕事であり、役割だなと思います。
長尾 JPTの目指す世界観とこれから手掛けたい社外事業、そして阿渡さんや僕たちの物語がつながっていくと、とても嬉しいです。
“エモイ”5年後のJPTを探って
——Edge Programの選考委員を務めた山田仁一郎氏との対話の中で、今後の会社の変革について話していました。どのような変革プランやビジョンがあるのでしょうか。
阿渡 設立時は前例のないことに取り組む0→1フェーズでした。そこでやったのがフルリモートやフルフレックス、社員1人が1プロジェクトを担当することでした。それが3年くらいで軌道に乗り、4年経った2024年度末は1→10のフェーズだと思っています。社員数も7倍になり、本社からも評価されて実績も上がってきました。
今はこの先の10→100を考えています。これまでは日揮グループの中の「重要だけど緊急ではない仕事」が中心でした。それは精神・発達障害などをもつ社員にとっては納期がプレッシャーになることに配慮したものです。でも2025年度からは、JPTの仕事を社外に広めていくためにグループ以外の仕事もこなせる仕組み作りをしていきます。これが整えられれば、社会全体として障害者雇用が進むし、働きたくても働けない人たちが働くようになるので、日本全体にとってもプラスのインパクトを生むのではないかと思います。
山田氏は、そうしたJPTのボトルネックを引き出して、僕たちに考えるきっかけを与えてくれました。Edge Programは10→100のための第一歩になったと思います。
——メンタリングで上がったその他のボトルネックや解決策について教えてください。
阿渡 10→100を目指す段階でのボトルネックは、サクセッションプランです。JPTが永続的になるために外部とエンジニアの橋渡しをするような人材が必要なので、2025年度からは社内で人材が育つような仕組みを考えています。
瀬野尾 2025年度は人事制度を変え、等級制度をつくることになりました。成果によって給与を変えるなどです。
長尾 ボトルネックという意味では、フルリモートによる従業員の情報格差というのがあります。事業の運営の質を高めてフルリモートのIT企業を突き詰めていくには、統一した情報にアクセスできるドキュメンテーションができると改善できるかなと思い、見直しているところです。
關 ボトルネックというよりも目標ですが、社会全体にとって良い事業やルールを見つけたい。フルリモート・フルフレックスは、ニューロダイバースの人にとってだけでなく、僕自身にとっても便利で良いルールです。JPTに携わることを弱者のための福祉活動やボランティアのように捉えられることがありますが、それは違います。自分も含めたすべての人にとって良いものは何だろうとずっと考えていて、それを見つけて社会に根付かせたい。JPTの従業員と対話しながら探していきたいです。
——山田氏との対話で上がっていた「JPTらしさ」とは?
阿渡 JPTはまだ若い会社ですし、僕自身もいずれ退くことになると思います。だから組織としてバラバラにならずにあり続けるためには、皆が共通して感じられる「これは大事にしよう」というJPTらしさを根づかせていきたいです。
僕は「対話」がキーワードだと思っています。例えば、社内のミーティングのルールも経営側だけで決めるのではなく、社員の意見を聞いて決めました。就業規則にないことを1人1人と対話で決めていくのが重要です。社員が本当の意味で望んでいることが何か、それを大切にするための対話がJPTの根幹だと思っています。
長尾 同感です。それに加えて、ハングリー精神がJPTらしさの1つだと感じます。障害者という枠組みの中で苦労した経験を経て、自分らしく働きたいという強い思いを感じます。自身の手を動かして成果を出し、それが満足感につながるという原理原則を今後も大事にしていきたいです。
關 皆それぞれ個性があって面白いのがJPTの良さです。色々な人がいるので、色々なアイデアが出てくる。これまでの1人1プロジェクトから、今後チームになったとき、その個性をうまく組み合わせることができればすごく強い集団になれると思います。
瀬野尾 組織のカラーに染めることなく1人1人が個性を表現でき、会社もその個性を大切にする企業を今後のJPTとしてイメージしています。
阿渡 みんなフラット。それが本来あるべき姿です。我々の特徴はお互いに「さん付け」で呼び合うこと。社長とか部長とか肩書きで呼ばない。もちろん役職とか役割はあるけれど、それは仕事の役割が違うだけでみんな対等ですから。
——メンタリングを経て変化したことを教えてください。
阿渡 山田氏のメンタリングの後、この4人の中で雑談が少ないということに気づきました。それで、毎週木曜日の夜10時からリモートで話すことにして、だいたい3時間くらいおしゃべりしています。「部室(ぶしつ)」と呼んでいますが、そこで出てくる話はけっこう大きい。
長尾 今は試行錯誤しながら布石を打っている時期という感覚があるので、“5年後にエモイことは何だろう”とか話しています。色々なエモさがあるけど、例えばJPTの働き方モデルを別の企業で実装できると良いな、とか。JPT社員がリードエンジニアとして伝承しに出向し、管理職になって帰ってくるとか。
關 長尾さんは物語を重んじる思想家なんです(笑)。僕は実務家で、JPTが障害者雇用のための特例会社ではなく高い実力をもった会社であると証明し、実力通りの給与が支払われるというのが5年後の目標です。
それから、メンタリングを受けながら、“有識者の方からのアドバイスを受けるためにはもっと試行錯誤が必要だ”と感じました。だからもっとチャレンジしていきたい。今はITに特化していますが、農業や漁業といった一次産業などにも事業の幅を広げていきたいです。
長尾 アグリテックには僕も興味があります。その先には地方自治体にサービス提供できる、可能性があると思います。
僕がメンタリングの中で意識したのは、インパクト投資です。それまで「2億あったらできること」とか、投資のことまでは考えていなかったけれど、投資してもらえるような事業を今後は考えたいと思いました。
阿渡 この記事を読んだ人がJPTと一緒に仕事をやりたいと思ってもらえたら嬉しいです。何事も面白がって一緒にチャレンジするような人たちと共にフラットな社会づくりに貢献していきたいですね。
(2025年3月14日 日揮パラレルテクノロジーズ本社にて 文:有岡三惠/Studio SETO 写真:村田和聡)