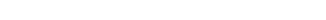イベントレポート
Farm to Fork——農場から食卓まで フードチェーンのあるべき姿を見直そう 食と農業のサステナビリティ シリーズvol.1
Date: 2022.06.08 WED
#グローバル動向
#気候変動
#自然資本
食と農業の領域では、食糧危機やフードロス、「生産〜加工〜流通〜販売〜廃棄」といったライフサイクル全体で排出されるCO2の問題までさまざまな社会課題が注目されています。GGPでは、こうした課題解決のアクションのきっかけをつくるため、2021年11月11日に食と農業のサステナビリティを考えるトークイベントを3名のゲストを迎えて開催しました。
最初のセッションでは、日本総合研究所 創発戦略センターの前田佳栄氏が、EUの「Farm to Fork(農場から食卓まで/以下、F2F)戦略」と日本の農水省が推進する「みどりの食料システム戦略」を紹介。そして自身が検討を進めているDXによる農産物の価値伝達の可能性を提示しました。続くセッションでは、パタゴニア プロビジョンズの近藤勝宏氏が、同社のリジェネラティブ・オーガニックの取り組みについて、日本サステイナブル・レストラン協会の伊地知由美子氏が、飲食店を軸にフードチェーン全体のサステナビリティを加速させる同協会の活動をそれぞれ紹介。最後のパネルセッションで、日本の食と農のフードチェーンをどう考えればよいのか、フードサステナビリティのために私たち消費者ができることは何か、について議論を深めました。
イベントレポート
Contents
| Session1 | EUの「Farm to Fork」戦略と日本の食と農のバリューチェーン 株式会社日本総合研究所 創発戦略センター・コンサルタント 前田 佳栄 |
| Session2 | リジェネラティブ・オーガニックに取り組む パタゴニア プロビジョンズ ディレクター近藤 勝宏 |
| Session3 | サステナビリティとレストラン 日本サステイナブル・レストラン協会 プロジェクト・マネージャー 伊地知 由美子 |
| Panel discussion | 株式会社日本総合研究所 創発戦略センター・コンサルタント 前田 佳栄 パタゴニア プロビジョンズ ディレクター近藤 勝宏 日本サステイナブル・レストラン協会 代表理事 プロジェクト・マネージャー 伊地知 由美子 株式会社ロフトワーク 執行役員 兼 イノベーションメーカー 棚橋 弘季 |
Session1 農場から食卓まで、フードシステム全体の変革が求められている
EUの「Farm to Fork戦略」と日本の「みどりの食料システム戦略」を読み解く
2020年5月に発表された「Farm to Fork戦略(F2F)」は、食料の生産、加工、流通、消費まで、システム全体を公正かつ健康的で環境に配慮したものに変革するための戦略として、欧州グリーンディールの中核として位置づけられたものです。「環境配慮はもちろん、農産物の輸出にも大きく関わることがポイントだ」と前田氏。
「F2Fでは、競争力や新たな機会の活用を重視。EUは、このフードシステムをグローバルスタンダードにすべく、今後はEU外の国との貿易協定にサステナブル条項を入れる可能性を謳っています。特に、日本のようなEU非加盟国からEU域内に食品を輸出する場合には、この基準を満たすことが必須になると予想されるため、注意が必要です」(前田氏)。
出所:European Commissionウェブサイト(https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en)
他方、日本では2021年5月に「みどりの食料システム戦略」が策定されました。
F2Fと同様にみどりの食料システム戦略も、生産だけでなくフードチェーン全体で持続可能な農業・食の実現を目指す戦略となっているのが特徴です。「ムリ・ムダのない持続可能な加工・流通システムの確立」「環境にやさしい持続可能な消費の拡大や食育の推進」「サプライチェーン全体を貫く基盤技術の確立と連携」といった包括的な取り組み項目が挙げられています。
また、環境負荷低減に向けたさまざまな目標数値が設定されています。
「有機農地※1に関しては、2050年までに全体面積の25%まで引き上げる戦略になっていますが、2018年時点で日本の有機農地は0.5%しかありません。この目標を達成するには、根本的なイノベーションが不可欠です」(前田氏)。
※1 補足
我が国では、有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)において、“「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業”と定義されている。
有機農業で生産された農作物のうち、コーデックス委員会のガイドラインに準拠した「有機農産物の日本農林規格(有機JAS規格)」の基準に従って生産されたものを「有機農産物」という。この基準に適合した生産が行われていることを第三者機関が検査し、認証された事業者は、「有機JASマーク」を使用し、「有機」「オーガニック」等と表示ができる。認証を受けていない農産物に「有機」「オーガニック」等の表示を行うことはできない。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/attach/pdf/meguji-full.pdf
出所:日本総研作成
出所:農林水産省
本当にその規格は適切ですか?DXによって農産物の価値伝達をアップデート
「現状、農産物の規格は、外見を重視したものになっています。しかし、本当に外見だけで農産物の価値を表現しきれているのでしょうか」(前田氏)。
生産に関わる課題だけでなく、食品流通が抱える問題解決にも注目し、農産物の新規格の必要性を前田氏は説きます。カブ農家で生まれ育った前田氏は、日本の農産物の評価に対して、長年ある疑問を抱いてきたからです。
例えば、畑の中をきれいに保ち、葉や枝のバランスを整えて風通しを良くすることで、病害虫の発生率を下げ農薬の散布量を減らすことができます。ただ、外見だけでは、そうした努力を表現することができず、価格に反映されることはありません。
このような観点から前田氏は「中身や農業者の努力を正当に評価できる指標がないことが問題」と、商品の品質や生産過程と価格設定の基準に関する問題点を指摘します。
「今後スマート農業が普及すると、農産物の価値評価はますます複雑になっていきます。農業も流通もDXが進む今こそ、農産物の規格もそれに合わせてアップデートが必要です」(前田氏)。
そこで、前田氏が新たに考案した独自規格が「CAV(Communication of Agricultural Value)スコア」です。CAVスコアは、センサーの測定値など合計100項目の指標を用いて、規格の構成要素と評価の段階を飛躍的に増やすことで、農産物の 「価値」を複合的に可視化しようとするもの。環境配慮や地域貢献などSDGsに関連した項目も加えることで、農業者の取り組み自体も評価できる規格にアップデートされています。
出所:日本総研作成
「さらにスマートフォンアプリなどを活用して、消費者の評価を生産者やメーカーにフィードバックする仕組みを整えることで、『栽培方法や出荷基準の改善』『生産者のモチベーション向上』『消費者が望まないオーバースペックな農産物の回避』にもつなげられる」と前田氏は言い、農産物の価値伝達を見直すことによる多くのメリットを提示しました。
Session2 パタゴニアがリジェネラティブ・オーガニックに取り組む理由
死んだ地球からは、ビジネスは生まれない
アウトドアスポーツ界のリーディングカンパニーであると同時に、環境危機や社会問題に対して責任をもってビジネスをする「レスポンシブル・カンパニー」の先駆者でもあるパタゴニアは、2016年より「パタゴニア プロビジョンズ」というフードビジネスをスタートさせました。「なぜパタゴニアが食品なのかの背景を語るには、創業当初までさかのぼらなければならない」と近藤氏は言います。
「三度の飯よりアウトドアが好き」と公言するパタゴニアの創業者たちは、自分たちのつくったウェアや道具を携えて世界中を旅しては、その経験をもとに新たな製品を生み出してきました。ところが、彼らは旅の途中で、変わり果てていく世界の光景を目の当たりにします。自分たちのビジネスが成長すればするほど、愛する自然が壊されていく——。
Tim Davis(C)2022Patagonia, Inc.
「環境活動家 David Browerの言葉『There is no business to be done on a dead planet.(死んだ地球からは、ビジネスは生まれない)』にある通り、地球を破壊してしまったら、一切のビジネスが生まれず、生活も立ち行かなくなります。そこでパタゴニアは、90年代初頭から本格的に環境課題に向き合うようになりました」(近藤氏)。
はじめに「大量に農薬を使用していたコットンを、すべてオーガニックに変更する」「フェアトレードの認証を受けた製品ラインアップを増やしていく」など、プロダクトの製造過程で生じたマイナスのインパクトをできるだけ0に近づけるためのさまざまな取組を重ねました。資源の搾取をはじめとする「環境への不必要な悪影響」を最小限に抑え、それでもビジネスが成り立つことを内外に示しました。
パタゴニアはさらに、地球が直面している気候危機を解決するにはもはや「マイナスから0へのサステナブル(持続可能)」では事足りず、「0→プラスへのリジェネラティブ(再生型)」つまりビジネスをすればするほど環境にとってプラスになるビジネスモデルを構築する必要があると考えました。そこで「無駄な消費を抑えるリサイクル素材採用推進」「関連企業も含めた再生可能エネルギーへの転換促進」「リジェネラティブ・オーガニックの拡大支援」の3つの取り組みを始めました。
「私たちは土に注目しています。農業が変わることで、地球を救うことができるかもしれない。土は炭素の貯蔵庫です。大気の2倍、植生の3倍、炭素の隔離能力があるとされています(※2)。それに私たちの食べ物の95%は土壌由来。健全な土を管理しながら農業を営むことが、環境危機の解決につながると考えているからこそ、パタゴニアはフードビジネスを始めたのです」(近藤氏)。
パタゴニアは、アウトドアと同時に三度の飯もやはり大事だと気づいたのです。
※2 補足
農地の炭素貯留は、2015年パリでの気候変動枠組み条約第21回締約国会議(COP21)でフランス政府が提唱した「4/1000イニシアティブ」で知られるようになった。世界の土壌に含まれる炭素量は大気中にCO2として存在する炭素の量の2~3倍に相当するため、土壌中に存在する炭素量を毎年0.4%ずつでも増えれば、毎年の人為的排出による大気中のCO2増加量を相殺できる。
https://www.mitsui.com/mgssi/ja/report/detail/__icsFiles/afieldfile/2021/04/15/2104i_nozaki.pdf
ただし、地球全体の土壌炭素量の推定値には幅があり、大気中のCO2の約3.3倍、陸上の植物バイオマスの約4.5倍に相当するとする研究結果もある。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/lca/7/1/7_11/_pdf
リジェネラティブ・オーガニックで地球を救う
パタゴニアはリジェネラティブ・オーガニックの拡大に向けて、農業団体や企業とともに「リジェネラティブ・オーガニック認証」という国際認証制度をつくりました。これは「土壌の健康」「動物福祉」「社会的公平性」の3本柱から成り、世界中でリジェネラティブ・オーガニック農法が採用された場合、世界の年間CO2排出量以上の炭素を隔離することができるようになると言います。
(C)Regenerative Organic(https://regenorganic.org/)翻訳
パタゴニアでは、このリジェネラティブ・オーガニック認証を取得した原材料を用いた製品の拡大に力を入れています。現在のラインナップは、多年草の穀物を使ったビールや、すべてオーガニック認証済・非遺伝子組み換え材料を使用した豆のスープ、魚体を傷つけない古くからの漁法で捕獲した野生のタイセイヨウサバ、水質と生物多様性を改善するムール貝のオリーブオイル漬など。「『パタゴニア プロビジョンズ』を通じて、食品の生産・加工の仕方や選び方を変えていき、地球環境を救っていきたい」と近藤氏は語りました。
Session3 なぜ地産地消と旬の食材の使用がサステナビリティに貢献するのか
食は、あらゆる社会課題に通じている
2010年に英国で食のサステナビリティ推進を目的に設立されたサステイナブルレストラン協会(以下、SRA)。同協会では飲食店などフードビジネス業界の方々が持続可能なフードシステムを実現するための自己評価ツール「Food Made Good 50(以下、FMG)」を開発し、1万店の飲食店に影響を与えています。また、このFMGを基準とした「世界のベストレストラン50」というアワードも開催しています。
SRAが飲食店を軸にしているのは、「生産から廃棄までのフードチェーンの中で、消費者に生産者の声を届けられる貴重な場だから」だと伊地知氏は言います。SRAにはミシュランの星付きレストランからファストフード店まで幅広いジャンルの飲食店が参加しており、サステナブルな食事を楽しみたい消費者はレストラン選びの基準としてSRAのレイティングを活用することができます。
レイティング項目は「調達」「社会」「環境」3つの柱と10の項目で現状を可視化し、飲食店・レストランのより良い運営を促進します。
出所:日本サステイナブル・レストラン協会作成
SRAの活動を通じて見えてきた課題を、伊地知氏は次のように語ります。
「森林破壊に気候変動、農薬や強制労働・児童労働、土壌や生物多様性など、食が影響を及ぼす社会課題は多岐にわたります。世界中で人為的に排出される温室効果ガスの3分の1は食に関するものと言われている。中でも、梱包・輸送・加工といった食料システムで、非常に大きなエネルギーを消費しています。国連の発表によると、2019年に消費者向けに提供された食品のうち、家庭や飲食業界などで廃棄された量は17%(ほぼ10億トン)にも上るそうです。私たちはフードチェーンを通じて、社会課題を深刻化させているのです」(伊地知氏)。
続いて、「地産地消と旬の食材の推進」について話を進めた伊地知氏は、食のグローバル化と巨大フードビジネスの弊害として、食材の単一化が進み、品種や味の多様性が喪失されていることを指摘。そのため、SRAでは「フードマイレージ(食料の輸送距離)が高くなる輸入品よりも、環境負荷の低い有機野菜の地産地消」を推奨していて、さらに「エネルギーの使用量が露地栽培の約2倍となるハウス栽培ではなく、露地栽培の旬の食材」の利用を奨めているそうです。
レストランが実践するサステナブルな取り組み
伊地知氏は、フードサステナビリティの課題を解決に取り組む事例として大阪のレストラン「BELLA PORTO」を紹介しました。
BELLA PORTO (KIMIYU GLOBAL)の自社農園
BELLA PORTOでは、自家農園を運営していて、スタッフ総出で畑を耕しています。自然に触れることで、スタッフの気持ちが豊かになったり、健康的になったりする効果も期待できます。自家農園で次に何がどれだけ収穫できるかがわかるため、メニュー開発を計画的に実施できると同時に、メニュー開発の創造力が膨らむそうです。また、余った野菜は乾燥させてパウダーにした上で、ケーキやクッキーに使用しているほか、それでも余った食材はコンポストで堆肥にして土に循環させています。
Panel discussion 分断されたフードチェーンをつなぎ直すために
最後に、パネルディスカッションを通じて、フードチェーンの課題解決に対し、「生産や流通における環境負荷の可視化」や「評価」という共通の軸で取り組んでいる実情が浮かび上がりました。また、「日々の食材選びやレストラン選びの際に、『サステナビリティに取り組んでいるかどうか』を基準にすること」、「これは『誰が、どこで、どうやってつくったものなんだろう?』など消費者自身も意識を高めることの必要性を語り合いました。
フードサステナビリティの問題は、決して1社だけで解決できるものではありません。ぜひアーカイブ動画をご視聴いただき、持続可能なフードシステムのあり方について、一緒に考えていきましょう。
アーカイブ
動画再生時間:約118分