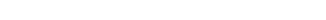イベントレポート
サステナブルな食文化を築くカギは「土壌」が握る 食と農業のサステナビリティ シリーズvol.2
Date: 2022.06.08 WED
#気候変動
#自然資本
私たち人間の食料生産を支える「土壌」。近年は、土壌の利用が温室効果ガスの排出にも関わっていることが分かってきました。そこでGGPでは、食と農業のサステナビリティ シリーズVol.2として、「土壌の再生と脱炭素」をテーマとしたトークイベントを開催しました。
トークイベントの最初のセッションでは、『土 地球最後のナゾ』(光文社、第7回河合隼雄学芸賞受賞)の著者であり、国立研究開発法人にて土の研究をしている藤井一至氏が、地球規模で見た土の現状を解説。続いて、イタリア在住で国際コンソーシアムJINOWAを主宰する齋藤由佳子氏が、循環型社会の実現と土壌再生に向けた取り組みを紹介。最後に、持続可能な調達にいち早く取り組むラッシュジャパン合同会社で原材料購買を行っている寺島 恵利香氏より、リジェネラティブなビジネスモデルへの取り組みをお話いただきました。その後のパネルセッションでは、ゲストの3名を交え、土壌という自然資本1を大切にしながら、持続可能で幸福な社会を築く方法について、議論しました。
1自然資本…森林、土壌、水、大気、生物資源など、自然によって形成される資本(=ストック)(環境省「環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書(2014年版)」)
イベントレポート
Contents
|
Session1 |
100億人を養う土壌を求めて |
|
Session2 |
世界中の「土」にこだわる企業を集めたコンソーシアムJINOWA |
|
Session3 |
リジェネラティブなビジネスモデルへの取り組み |
|
Panel discussion |
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所主任研究員 藤井 一至 |
Session1 土の可能性を信じて、再生と生成に挑む
世界の収容可能人数は限界に近づいている?
藤井氏のセッションでは、土壌と環境・社会課題の関係が解説されました。
人間が住みやすい土地とは、水と、食物が育つ「良い土」がある場所です。人類の歴史を振り返っても、生産力の高い「良い土」がある地域に人口が集中し、文明が興りました。
それでは、「良い土」とはどのような土なのでしょうか。
藤井氏は「粘土と腐植に富み、窒素、リン、ミネラルなど栄養分に過不足なく、酸性でもアルカリ性でもない(中性)、排水性と通気性が良い土壌」と定義しています。さらに、このような「良い土」は世界に局在しているのです。
「その土地の環境や条件によって土の種類が異なります。地域の土の種類ごとに人口密度を比較してみると、土の質としてはそこそこな『黒ぼく土』がある日本は人口密度が高い。一方、酸性で栄養分の乏しい『オキシソル』という土がある南米は、人口密度は低くなっています。このように土の種類と人口密度は、大いに関係しています」(藤井氏)。
このように、土の種類が変わると、同じ面積あたりの農業の生産力が変化し、同じ面積あたりで養うことができる人の数が変動します。つまり「肥沃な土地が平等に行き渡っていないこと」は食糧問題に直結する問題です。
私たちが1年間で消費する穀物を確保するには、1人あたり0.1haの土地が必要とされていますが、世界の約15億haの畑で収穫される予定の穀物を均等に分配できたとしたら、150億人が暮らせる計算となります。しかし、実際は世界70億人のうち1割の人たちが飢餓で苦しんでいます。
さらに、農業は「土の養分を作物に蓄えて畑から持ち出すこと」だということも、忘れてはいけません。農業で土を使えば使うほど、養分は目減りし、土は劣化していきます。土の養分は土壌微生物の働きや水や空気の循環によって蓄えられますが、植物や微生物の力でわずか1cmの厚さの土を回復するには、百年から千年という長い年月が必要です。
現在、世界の陸地面積のわずか11%しかない肥沃な土地で、世界人口の8割(=60億人分)の食糧がつくられています。限られた肥沃な土地に、莫大な負荷をかけ続けているのです。
だからこそ「『土は劣化するものであり、養分補給が必要なものだ』と認識し、人間の手によってメンテナンスしていくことが大切だ」と藤井氏は強調します。
出所:MDB技術予測レポート(2022年、藤井一至)
土壌環境の向上は地球温暖化の緩和の一手に
さらに、藤井氏は、土が持つ「炭素貯留の効果」についても紹介しています。土を肥沃にする有機物の多くは炭素で構成されています。もし土壌中の有機物の量を毎年0.4%ずつ増やすことができたとしたら、工場から出る二酸化炭素をすべて吸収できるようになると唱える研究者もいます。このことから、土壌環境をよくすることは「地球温暖化の緩和」としても期待されています。
出所:『土 地球最後のナゾ』(光文社新書、藤井一至)
「土の豊かさによって食文化は豊かになっています。日本の水田稲作のように2000年続いた農業は世界のどこにもないんです。日本はもっと独自の土壌の強みを活かすべきだし、耕作放棄してしまうのはもったいない。これからも各地で多様な食文化を楽しめる未来にするためにどうすれば良いのか、みんなで考えていく必要があると考えています」(藤井氏)。
環境・社会課題解決が求められる今、食料生産を継続しつつ、「劣化土壌の修復」と「土壌への炭素貯留技術の発展」が求められています。
Session2 あらゆる産業が土を良くする社会を目指して
伝統知を失った先にある地球の未来
居住地であるイタリアで、2021年5月に暮らしのすべてを土へ還す循環創出コンソーシアム「JINOWA」を立ち上げた齋藤氏。JINOWAでは「あらゆる国の地域と産業が地球の土をより良くする世界を目指す」というテーマを掲げ、商品やサービスを通して土の再生や肥沃化に貢献する商品開発や研究などを行う事業者をつなぐ活動をしています。
JINOWAの取り組みの一つに、建築家 遠野未来氏の建築作品を起点とした社会循環デザインの実証実験「JINEN」があります。この建築作品はヴェネチアの自然素材のみを使用しながら、展示期間を終えると解体して土に還し、新たな素材やプロダクトとして循環するよう設計されています。まさに「暮らしのすべてを土へ還す」というコンソーシアムのコンセプトを体現したプロジェクトです。
齋藤氏が土に興味をもったのは「日本には、微生物と共生し、マイクロバイオーム(ヒトの体に共生する微生物)を活かす数多くの伝統知を持っている」ことに気づいたことがきっかけでした。
日本の歴史では、焼畑農業をしていたり、遺跡には炭を使って土壌改良していた形跡が見られたりと、土壌を保つために人の手が加わっていることが分かっています。また、腐敗を遅らせるために、灰や柿渋などの自然素材を使って、「菌との共生」を豊かに積み重ねてきました。そんな伝統知がほぼ失われてしまったことが課題であると齋藤氏は語ります。
「長年、培われてきた『土と向き合う技術』を継承しなければならないと感じるとともに、土壌が滅びると文明が滅びることは間違いないという想いを強くしています」(齋藤氏)。
出所:齋藤氏登壇資料より
土へ還すことから始まる真の循環デザインへの挑戦
食に限らず、私たちは利便性や経済合理性を追求し、微生物による分解が難しい製品を製造しています。
「南米の砂漠にある“ファストファッションの墓場”と言われる場所には、毎年3万9,000tもの不要になった服が運び込まれて山積みにされています。自然分解されるまでに途方もない年月が必要になり、自然素材のコットンならおよそ1年、ポリエステルだと200年もかかってしまいます。ごみの山から脱却するためには、衣食住のあり方を本気で見つめ直さなければなりません。」(齋藤氏)
また、ヨーロッパはサーキュラーエコノミーへのシフトが進んでいて生分解や堆肥化に優れた製品であふれているイメージがありますが、実際は「裏側の仕組み(=循環デザイン)がまったく追いついていない」と齋藤氏は指摘します。
『循環』を実現するには、各地域の特性に適したやり方を考えながら、複雑に絡んだ循環のプロセスに絡み合うつながりを実践的にデザインしていく必要があります。土に還る素材の工夫だけでなく、実際にそれが土に還るプロセスも併せてデザインしなければ、循環型の社会へのシフトにはつながりません。JINOWAがコンソーシアムという形をとり、複数の企業をつなげているのも、こうしたプロセスのデザインを重視するからです。
「循環型社会と言いながら、時間をかけて輸送して大型プラントに運び込むといった従来のモデルのままでは、まったく意味がない。いかに分散型で地域に根差した『小さな循環』をたくさんつくっていけるかが、今後の挑戦になってくると思います」(齋藤氏)
出所:齋藤氏登壇資料より
最後に、土壌の問題は農業だけに関わる問題ではないことも強調しました。
「日本は、自然の素材をうまく使って菌と共生しながら、分解して土に還すことを何百年もやってきた国。土を良くすることは、農業だけに閉じて行うものではありません。あらゆる産業は土を無視できないという前提に立ち、みなさんと一緒に土の再生や肥沃化に貢献する方法を考えていきたいです」(齋藤氏)。
Session3 リジェネラティブなビジネスモデルへの取り組み
ラッシュが目指すこと
イギリス発祥で、世界48の国と地域で900店舗以上を展開しているラッシュ。1995年の創業時から、フレッシュでオーガニックなフルーツや野菜を使ったハンドメイドの化粧品を製造しています。また、人権、動物の権利、環境保護に関する社会課題に対してアクションを起こす企業としても知られています。
ラッシュジャパンで原材料購買を担当している寺島氏は、セッションの最初に、2019年にラッシュで策定した、自らのありたい姿のプランについて紹介しました。
このプランでは、「全てのニーズに応じた商品を作る。」「全てのカテゴリーでナンバーワンになる。」「地球を救うためのコスメティックレボリューションを起こす。」という意欲的な目標を掲げるとともに、従業員一人一人が自ら考え、学び、行動できるよう、社内で学びの機会が設けられました。一人一人が生み出した小さな変化の積み重ねが、プランの達成へと近づく一歩だと考えられているからだと寺島氏は言います。
出所:ラッシュ・シークレットマスタープラン
このプランの一環として、ラッシュでは、商品に使う原材料の購買活動を通じて地域社会や⾃然環境を再⽣し、元来そこにあった豊かさを取り戻すことを⽬指した『リジェネラティブ(再生)バイイング』を行っています。
リジェネラティブバイイングでは、「環境課題の解決と商品づくりを紐づけて考えること」「地元の人を含むさまざまな団体とワーキンググループを作ること」「原材料購買に直接関係しないところにも目を向けること」の3つを大切にしています。その一例として、寺島氏は、アンダーユーズの問題(休耕地の増加など資源を十分に活用しないことによる問題)に取り組んでいる「渡り鳥プロジェクト」を紹介しました。
ラッシュのリジェネラティブバイイングを体現した「渡り鳥プロジェクト」
「渡り鳥プロジェクト」でラッシュが注目したのが、人里近くに生息する「サシバ」という渡り鳥。
サシバは里山の生態系ピラミッドの頂点に君臨する猛禽類でありながら、人的な自然環境破壊によって、絶滅危惧種に指定されるほど生息数が減っています。かつて稲作や畑作が盛んに行われていた日本の里山では、サシバのエサとなるカエルやヘビなどの両生爬虫類、バッタやセミなどの昆虫類が数多く生息していました。しかし、耕作放棄地が増加し、里山に人の手が入らなくなると、生物多様性が損なわれ、サシバにとって生きづらい環境になるのです。
そうしたアンダーユーズの悪循環から脱却すべく、ラッシュでは、商品の原材料として日本各地の里山で生まれた資源を活用しています。例えば、米からはフレッシュフェイスマスクや洗顔料がつくられ、米を収穫した後のワラからは、ギフト用のボックスとして「サシバボックス」を商品として展開しています。
「微力ではありますが、ビジネスを通して購買を続けながら、少しでも多くの方に日本の課題を知ってもらい、里山再生に興味・関心を持ってもらうことが重要だと考えています。また、こうした活動には私たちのバイイングポリシーに賛同してくださるサプライヤーや、私たちと行動を共にしてくれる団体やボランティアのみなさんの協力が不可欠です。より多くの方々を巻き込みながら、緑豊かな世界を残していけたらと考えています」(寺島氏)。
Panel discussion 共創による多様性の受容が持続可能な社会への近道
パネルディスカッションメンバー。寺島氏(上段左)、棚橋氏(上段中央)、藤井氏(上段右)、齋藤氏(下段左)、武田氏(下段右)
最後は、3名のゲストとモデレーターのロフトワーク 棚橋弘季によるパネルディスカッションを実施。土壌という自然資本を大切にしながら、持続可能で幸福な社会を築く方法について考えました。
「先進国では自然資本のアンダーユーズが問題になるが、途上国ではオーバーユーズが問題となっている」「化学肥料がなければ3人に2人が食べていけなくなるという現実と、化学肥料の使いすぎによっては土壌酸性化や温室効果ガスの排出の増加を招く」という藤井氏の解説を受け、現在の自然資本の利用を見直さなければ、持続可能でないことが明らかとなりました。また、土壌について考える上では、農業にたずさわる人たちだけでなく、さまざまな領域の企業同士が共創し、バランスを取ることが重要だと議論が発展しました。
ぜひアーカイブ動画をご視聴いただき、これからの食と農業にまつわる具体的な取り組みについて、GGPと一緒に考えていきませんか?
アーカイブ
動画再生時間:約121分