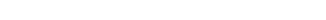イベントレポート
岐路に立つ日本の農業、「スマート化」で未来の産業に 欠かせぬ食料安全保障の視点
Date: 2023.10.20 FRI
#気候変動
#イノベーション
#自然資本
2023年8月3日、GGPは東京大学国際オープンイノベーション機構と共同で「サステナブルな社会に向けた産学連携 どうなる日本農業?~『食料・農業・農村基本法』改正の議論を踏まえた持続可能なフードシステムの在り方」と題したイベントを開催しました。
ロシアによるウクライナ侵攻による世界的なフードシステムの混乱は、食料安全保障の重要性を改めて私たちに突きつけました。日本は食料自給率が4割に満たず、少子高齢化などの影響で農業従事者は減り続けてきました。農業の再生は喫緊の課題であり、農業政策の根幹である「食料・農業・農村基本法」(以下、「基本法」)の改正に向けた議論が進んでいます。
イベントでは、東京大学 大学院農学生命科学研究科教授の中嶋康博氏、日本総合研究所創発戦略センター エクスパートの三輪泰史氏など法改正の議論にも携わる専門家を招き、産学、そして農家と連携した課題解決策について議論しました。
モデレーターはフリーアナウンサーの三宅民夫氏が務めました。
東京大学大学院農学生命科学研究科教授・中嶋 康博氏、日本総合研究所 創発戦略センター エクスパート・三輪 泰史氏とモデレーターの三宅 民夫氏
農業はフードチェーン全体の10分の1程度しかない
イベントの冒頭、東京大学国際オープンイノベーション機構・統括クリエイティブマネージャーの上條健氏が登壇し、日本の農業が抱える課題の概要を解説しました。食料の生産から加工、流通、販売、そして消費に至るフードチェーンの国内市場規模は117兆円になる一方、農業はその10分の1程度の10兆〜11兆円にとどまっている現状を提示。農業の付加価値を高めていく必要性を指摘しました。
「日本も農作物だけではなく、加工品なども含め付加価値を高めて輸出につなげていくのも1つの方向性だろう」と述べ、アメリカに次ぐ農業輸出国であるオランダの事例を紹介しました。デジタルトランスフォーメーション(DX)やグリーントランスフォーメーション(GX)、健康志向などの広がりも、付加価値を高めるきっかけになると期待をかけました。
上條氏は学術的な立場から「知識や技術を産業界に移転していくだけではなく、課題や能力、知識、経験をオープンにしていき、成長産業として農業・安定的で信頼性の高いフードシステムを作ることに貢献していきたい」と抱負を語りました。
歴史的転換期、食料安全保障の観点欠かせない
次に登壇した東京大学大学院農学生命科学研究科教授の中嶋康博氏は、基本法の見直し議論の経緯を通じて、日本の農業の課題を解説しました。基本法の改正は今秋、最終的な取りまとめがされる見込みです。法改正の背景には「日本の農業は歴史的転換期にある」(中嶋氏)との認識があります。
農業政策の根幹となっている「食料・農業・農村基本法」の改正に向けた議論が進んでいる 図提供:中嶋康博 資料:食料・農業・農村政策審議会「我が国の食料・農業・農村を取り巻く状況の変化」(2023年9月29日)
中嶋氏は「基本法は制定されてから20年が過ぎた。ロシアのウクライナ侵攻を引き金に国際的な農産物の価格が高騰したことで、食料安全保障の観点からこの枠組みを考え直さないといけないとの問題意識が高まった」と改正議論の経緯を説明しました。
中嶋氏は、「1990年代の世界の食料需給は束の間の安定期で、基本法はそれを前提にした政策体系だったのではないか」との見方を示しました。当時、冷戦が終結し、世界貿易機関(WTO)協定が締結され、かつ日本は経済力があり輸入もしやすかったという状況がありました。
小麦などの食料輸出価格は1970年代に上昇した後、1990年代まで安定し、2000年代に入って再び上昇している 出典:FAOSTAT
しかし2000年代に入ると状況が変化します。世界ではウクライナとロシアが食料の輸出国として台頭し、グローバルサウスを中心とした人口が増えている地域の食料需要を賄うという「地政学的な変化」(中嶋氏)が発生。一方、日本経済は低迷し国際的な購買力が低下していきました。
ロシアとウクライナの小麦輸出量が2000年代に入って急増している 出典:FAOSTAT
かつて8割あった食料自給率は4割以下に、生産急減が原因
国内では、食料自給率の低下が深刻な状況にあります。かつて80%を超えていたカロリーベースの食料自給率は、現在40%を下回っています。これまでも45%に高める目標を掲げてきましたが、全く達成されず、逆にじりじりと低下しています。
自給率は生産量を消費量で割り算して出します。最近は少子高齢化で消費は落ち込んでおり、生産量を維持していれば自給率は上昇するはずです。しかし、そうならないのは生産量が消費の低迷を上回る速度で減少しているからです。
カロリーベースの食料自給率は8割超から4割以下に減少した 図提供:中嶋康博 資料:農林水産省「食料需給表」 2012年度は概算値
農作物の価格が上がらないために農業の収益率は低迷し、担い手が減り、投資も進まず、耕作放棄地も増えるという悪循環に陥っています。中嶋氏によれば「技術革新も進んでいるが追いつかない」状況です。その背景には、景気の低迷、摂取カロリーの減少などがあり、消費が90年代半ばから減り続けいます。これが「ボディーブローのように効いて農業生産の成長を押しとどめている」(中嶋氏)のです。
ただし、中嶋氏は「まだ余地はある」と指摘します。基本法改正の中間取りまとめでは、デジタル技術などを活用したスマート農業の推進や、農業支援サービスなどを活用するほか、適正な価格転嫁、環境への配慮や食料安全保障のための法整備などが提示されています。中嶋氏は、「このまま農業生産が伸びなければ食料安全保障上、大きな問題となる」と改めて強調し、基本法改正の意義を説明しました。
農業生産、V時回復の可能性もある
日本総合研究所・創発戦略センターエクスパートの三輪泰史氏は、中嶋氏による日本の農業の現状整理を踏まえ、より具体的にスマート農業などを活用した課題解決策について解説した。三輪氏は「日本の農業は崖の下に転落していっているように思われるかもしれないが、下げ止まってV字回復の可能性もある」と前向きに訴えました。特に、環境負荷の軽減などサステナビリティ(持続可能性)への配慮は「従来は(コストの上昇要因で)足かせと捉えられていたが、これからは『もうけるため』に実践する時代にしていく必要がある」と指摘しました。
三輪氏は、農業におけるサステナビリティは、「事業面」「環境面」「社会面」の3つの視点から取り組む必要があると指摘しました。モノのインターネット(IoT)や人工知能(AI)、ロボティクスは、この3つのサステナビリティを実現するための武器となります。
三輪氏が考える農業のおける「3つのサステナビリティ」 図作成:三輪泰史
ドローンの活用を例に挙げると、ドローンに搭載したカメラやセンサーで土壌の状態を見える化すれば、病気が発生したり成長が遅れたりしている場所にピンポイントで肥料や農薬を散布できます。それにより、肥料や農薬の使用を減らしコストを下げられる可能性があります。しかも、環境負荷の軽減にもつながり、肥料や農薬の輸入依存度も下げられ食料安全保障にも寄与します。
ドローンを活用して土壌の状況を可視化することで、肥料や農薬の使用を効率化し「3つのサステナビリティ」を向上させることができる 図作成:三輪泰史 写真:農林水産省、DONKEY、セキュアドローン協議会
三輪氏は、「これまでバラバラだった取り組みを1つに束ね、ムーブメントを作っていくことが大切になる」と指摘しました。その1つとして、農業支援サービスを例に挙げました。農業従事者の高齢化が進む中、IoTなどのスマート化を本当に実践できるのかと懸念する声もありますが、「IoTが分からなくても、専門の企業や団体がサポートすれば農業のスマート化は可能だ」(三輪氏)と述べました。
IoTなどが分からない農業従事者でも、支援サービスを使えば農業のサステナビリティは向上できるようになる 図作成:三輪泰史
「何よりも大切なのが、消費者の行動。『いいものを安く』ではなく、農業従事者が適切な対価を受け取れるようにすることが、日本の農業を次にステージに進める上で極めて大切だ」と強調。「日本全体で所得が上がらない不都合を農業に押し付けるのはアンフェアだ」と訴えました。
環境配慮や社会貢献といった付加価値の対価を得られるようにする仕組みが必要となる 出典:日本総合研究所
農業を「守る」のではなく産業創出の視点を
パネルディスカッションでは、モデレーターを務めたフリーアナウンサーの三宅民夫氏が、事前にイベント参加者から集めた質問や意見を紹介しながら議論を進行しました。「持続可能な農業の未来を具体的にイメージしたい」といった声に対して、中嶋氏は「やや悲観論に基づいた議論をしているが、ポテンシャルはある。ただ、技術革新には投資に加えて、関連産業や農家自身の参画も必要になる」と課題を示しました。
三輪氏は「農家の減少により、農家1人あたりのマーケットは大きくなっている。これはチャンスだが、これまでは生かすことができなかった。農地を増やしても人手に頼るだけでは限界がある。農業をビジネスとして捉える視点が欠かせない」と指摘しました。
三宅氏は「農家は年配の方が多く、技術を使いこなせないのでは」と疑問を投げかけました。これに対し三輪氏は「これまでは『こんなの使えない』という声もあった。技術先行で議論されてきたのは反省点。最近は技術も使いやすくなった。なんでも自分でやるのではなく、地域全体で技術を導入したり、技術を使える人に頼ったりする選択肢もある」と応えました。
中嶋氏は「農業の難しさの一つは季節性。日本の国土は縦に細長く、同じ作物でも産地がどんどん移動していく。外部の企業や団体がサービスを提供する形にすれば、農家は必要な時だけ技術を使え、事業者は移動しながら全国の農家にサービスを提供できる。農家の技術導入コストを下げられるほか、機械の稼働率も上がって効率がいい」と新たなビジネスの可能性を示しました。
三輪氏は「これまでのスマート農業は『従来の農業を守るため』という発想が強かった。これからは既存の農業の延命ではなく、未来に向けて新しい産業を創造するためのスマート農業にしていかなければならない」と強調しました。
最後に、三宅氏が産学連携を進めていくためのポイントを問いました。中嶋氏は「技術革新は非常に重要な要素。消費者が何を求めているかを川中(の流通)、川上(の生産者)に反映させて、消費者ニーズに応える技術の開発が必要になる」との考えを述べました。三輪氏も「産学と農業従事者の距離が遠いのも課題。産学連携の成果を農家が使う、というのではなく、(新たな技術などの開発に)産学だけではなく農家自身が関わることが大切になる」と指摘しました。
三宅氏は「社会を動かしている私たちは諦めてはいけない。産学連携でフードシステムに革命が起きることを期待している」という参加者の声を紹介し、閉幕しました。
(文:大竹 剛/エディットシフト、写真:工藤朋子)