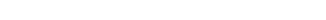解説記事
スマート農業が拓く、日本の農業の持続可能性(前編)
Date: 2025.09.24 WED
#初学者
#自然資本
#新規事業
#気候変動
日本農業の抱える課題とスマート農業への期待
日本の農業は近年、農業従事者の高齢化と減少、深刻化する気候変動、資材価格の高騰といった複合的な課題に直面しています。これらの課題を乗り越え、持続可能な農業を実現するための切り札として、スマート農業への期待が高まっています。
なぜスマート農業が注目されているかを紐解くため、まずは国内農業の現状と課題を振り返ってみましょう。図1の通り、農業の総産出額は9兆円台(2023年)となっています。中長期的に国内農業の総産出額は逓減してきましたが、近年は農業の成長産業化政策の効果もあり、少し盛り返してきている状況です。
図1 農業の総産出額 出所:農林水産省「令和6年度 食料・農業・農村白書」 ( )内の数値は、各年の農業総生産出額に占める部門別の産出額の割合(%)
一方で、国内農業の足腰はかなり弱っている状況です。
深刻な課題の1つが農業従事者の高齢化と減少です。
農林水産省統計によれば、基幹的農業従事者数は年々減少しており、2000年の半分の水準にとどまっています。加えて、農業者の平均年齢は70歳近くに達しており、今後ベテラン農業者の離農がさらに加速すると予測されています。これは、長年培われてきた熟練の技術や知識が次世代に十分に継承されず、多くの耕作地が放棄されるリスクが高いことを意味しています。
また、気候変動の影響が顕在化しています。近年、猛暑、豪雨、干ばつが頻発し、農作物の生育に甚大な被害をもたらしています。いわゆる“令和のコメ騒動”も、その背景に2年連続の猛暑による供給力の低下があると指摘されています。
このように、農作物の収穫量の不安定化は、農業経営を圧迫するだけでなく、消費者の食卓にも影響を及ぼし、ひいては日本の食料安全保障を脅かす事態に発展しかねないと言えます。
このような状況を受け、2024年には食料・農業・農村基本法が約25年ぶりに改正されました。筆者も審議会委員として改正に向けた検討に携わりましたが、これまでと同じ農業モデルは継続できないという意見が多く出されました。新しい農業に向けた議論においては、食料安全保障、サステナビリティ、グローバル化、スマート化などが主な論点となりました。
期待高まるスマート農業——技術革新が農業を変える
このような複合的な課題に直面する中で、農業に新たな光を灯すのが、基本法改正でもクローズアップされたスマート農業です。
スマート農業とは、ロボット技術、ICT、AIなどの先端技術を活用し、農業における生産性や品質の向上、省力化、コスト削減、環境負荷低減などを図る新たな農業のあり方です。
図2のように、自動運転農機、ドローン、ロボット、AIといった先端技術が農業の現場に導入され、これまでの常識を覆すような変化をもたらし始めています。
図2 スマート農業の分類 図作成:三輪泰史
農林水産省の事例集をもとに、スマート農業による効率化を見ていきましょう。ある水稲農家では、自動運転トラクターの導入で水稲の春作業における労働時間を約25%削減することに成功しています。また別の農業者では、ドローンによる農薬散布により、従来の作業と比べて時間を約9割も短縮できたと報告されています。
加えて、スマート農業は経験の浅い農業者のノウハウ不足を補う効果もあります。これまで熟練農家の「勘と経験」に頼ってきた部分を、客観的なデータと科学的な知見で補完し、再現性の高い農業を実現することが可能です。これまで若手農業者からは、10年経っても半人前扱いされるとの声も聞かれましたが、今後は就農直後から合格点が取れるようになります。さらに言えば、デジタルネイティブな新規就農者の方が高いパフォーマンスを出せる場面もあるでしょう。
スマート農業を推進する政策
このような新たな農業モデルであるスマート農業を推進するため、さまざまな施策が講じられています。
基本法改正でスマート農業の重要性が謳われたことに加え、2024年にはスマート農業技術活用促進法が施行され、スマート農業技術の研究開発や普及、人材育成などが法的に後押しされることになりました。
これにより、農業現場への先端技術導入が円滑に進むための基盤が整備されたと言えます。また、2025年には農水省主導で、農業者、農機メーカー、食産業企業、研究機関、行政などが連携を推進するスマート農業イノベーション推進会議(略称:IPCSA)が発足しました。
こうした法整備や組織体制の構築は、スマート農業が単なる個別の技術導入に留まらず、農業全体の変革につながると期待されます。
スマート農業の普及により、農業を「汗をかく、きつい仕事」という旧来のイメージから、「知識と技術を駆使するクリエイティブで先進的な産業」へと変えることができ、若者や異業種からの参入を促し、新たな担い手の確保に繋がる大きな一手となります。