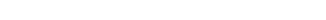解説記事
企業フィランソロピーの潮流と意義
Date: 2025.10.15 WED
#初学者
#ソーシャル
#ESG投資・開示
日本総合研究所 瀬名波雅子
フィランソロピーとは何か
私たちは今、気候変動、貧困・格差、少子高齢化、地方創生など、さまざまな社会課題に直面しています。こうした社会課題に対する取り組みを「フィランソロピー」を切り口に考えてみたいと思います。
フィランソロピー(philanthropy)という言葉は、ギリシャ語の「philos(愛)」と「anthropos(人類)」を組み合わせた言葉で、博愛、人間愛という意味が語源です。
19世紀後半からアメリカで広がり、当初は富裕層の寄付行動を指す言葉でした。この頃アンドリュー・カーネギーやジョン・D・ロックフェラーといった実業家が、莫大な財産を公共の利益のために投入して現代フィランソロピーの基盤を築いたことが知られています。
一方、日本のフィランソロピーは「企業の社会貢献」の文脈で普及しました。1980年代後半、アメリカに進出した日本企業が現地で寄付やボランティアなどのフィランソロピー活動に触れ、企業も一市民としてさまざまな社会貢献活動を期待されたことで日本でも関連した動きが出てきます。
日本における、企業のフィランソロピー活動
1990年には「経団連1%(ワンパーセント)クラブ」が設立。経団連が法人会員に対し「経常利益の1%を寄付に回そう」と呼びかける取り組みを始めます。また民間企業が協力して文化・芸術振興を支援する「企業メセナ協議会」も設立されるなどしたことから、1990年は「フィランソロピー元年」とも呼ばれています。
現在「フィランソロピー」という言葉の定義において明確に定まったものはありませんが、ここではロバート ・L・ペインの「民間による自発的な公益活動(Voluntary action for the public good)」(1988)という意味で使用します。
この定義を前提に、企業のフィランソロピー(社会貢献)活動について以下の3つの分類に分けて考えてみたいと思います。
① 資金的支援
② 非資金的支援
③ 社会的事業とフィランソロピーを組み合わせた活動
1つひとつ見ていきましょう。
① 資金的支援
企業が直接NPOなどの非営利セクターに寄付を行う支援です。経団連が2025年に公開した「社会貢献活動に関するアンケート」結果によると、回答企業153社のうち92%が資金的支援(寄付)を実施しています。
出所:日本経済団体連合会「社会貢献活動に関するアンケート」結果
企業による資金的支援には、直接の寄付だけでなく、企業が財団を設立して寄付や助成金を提供する方法もあります。
ヤマト運輸は東日本大震災の発生を受けて「宅急便1個につき10円寄付」の仕組みをつくり、1年間で142億3,600万円超の寄付を集めました。この寄付は同社の財団を通じて被災地へ届けられました。[*1]
また、従業員が行う寄付に企業が一定額を拠出し上乗せする「マッチング・ギフト」制度もあります。
たとえば三菱電機では、1992年に「三菱電機SOCIO-ROOTS(ソシオルーツ)基金」を立ち上げ、従業員からの寄付に対して会社が同額を上乗せし、児童養護施設等の福祉施設や被災地への復興支援への寄付を続けています。[*2]
② 非資金的支援
自社の製品を寄付したり、本業で培った技術やノウハウを社会課題の解決に活用したりという取り組みです。
例えば、災害時には多くの企業が避難所に自社が製造する食品や衣料品、医薬品などを救援物資として提供しています。
トヨタ自動車は、災害復旧支援の取り組みを継続的に行う企業の1つです。被災地での車両の貸し出しや、やむをえず車中避難となる場合のリスクとその予防法、平時の備えの啓発活動に取り組んでいます。[*3]
また、銀行、証券会社、生保・損保などの金融機関による金融経済教育が活発です。お金や金融の仕組みなどについて、初等教育から高等教育まで現場に出向いた教育活動が行われています。
③ 社会的事業とフィランソロピーを組み合わせた活動
社会課題解決に取り組むビジネスとしての活動と、企業が社会のために無償で自発的に行うフィランソロピー活動を組み合わせた取り組みです。
住友化学は、ポリエチレンに殺虫剤を練りこむという従来工場の虫よけ網戸に使われていた技術を用いて、虫よけの蚊帳「オリセット®ネット」を開発しました。[*4]
マラリアによって亡くなる人はいまも年間約59万7千人おり(出所:World malaria report 2024)、その対策として蚊帳は手軽に利用できるものです。
オリセット®ネットは2001年にはWHOから世界で初めて長期残効型蚊帳としての効果が認められ、使用が推奨されました。
主にUNICEFなどの国際機関が購入し、世界80カ国以上で無償供与されてきました。オリセット®ネットの普及が進んでいる地域では、マラリアの罹患率が低下するなど、その効果が実証されています。
また住友化学はオリセット®ネットの収益の一部を寄付し、NGOと連携してアフリカなどで小中学校の建設を支援するほか、アフリカの貧困地域へのオリセット®ネットの寄付も続けています。[*5]
企業のフィランソロピー活動の潮流と課題
③のように、社会的事業と社会貢献事業を組み合わせた活動は、近年広がってきています。
従来のように利益が出たあとで社会貢献活動を行うという順番ではなく、企業がもつ資源や経験を生かして社会的課題に取り組み、新しい商品や仕組みを提供し社会的な価値を生み出す活動です。近年はSDGsを背景に持続可能な社会を目指す事業への注目が高まっており、こうした活動への評価が企業価値を高めることにもつながっています。
「本業か、フィランソロピーか」という二項対立ではなく、「本業も、フィランソロピーも」という融合が生まれているのです。こうした活動は社会的価値と経済的価値を同時に生み出し、新しい可能性を広げています。
社会課題の解決において企業の取り組みは大きな推進力になる一方、単一の企業にできることには限界もあります。
複雑で多面的・構造的な社会課題に対峙する際に重要となるのが、異なるセクターとの協働です。
一筋縄では解決できない社会課題に対し、異なる立場である企業や非営利組織、行政、アカデミアなど多様なステークホルダーが対話を重ね、お互いの強みや知恵、資源を提供し合うことは今後ますます求められるでしょう。
持続的な対話と協働のプロセスを通じて多様な視点を得ることは、企業にとって、社会の中で果たすべき役割を明確にし、さまざまな事業につながる可能性を拓く鍵になっていくと考えています。
*1 助成先の復興再生事業について、2015年2月のご報告です。|東日本大震災復興支援に向けた寄付について|ヤマトホールディングス株式会社
*2 三菱電機SOCIO-ROOTS(ソシオルーツ)基金 | 地域社会との共生 | 社会貢献活動 | サステナビリティ | 企業情報 | 三菱電機
*3 トヨタ災害復旧支援 TDRS:Toyota Disaster Recovery Support
*4 感染症への取り組み | コミュニティへの貢献 | 住友化学株式会社
*5 「オリセット®ネット」33万張りをミレニアム・ビレッジへ寄付 | サステナビリティ | 住友化学株式会社
【参考文献】
谷本寛治『企業と社会』中央経済社、2020年
細海真二『相互関係フィランソロピー 包摂社会を求めて』大阪公立大学出版会、 2025年
公益社団法人日本フィランソロピー協会『共感革命: フィランソロピーは進化する』中央公論事業出版、2021年
坂本治也『日本の寄付を科学する――利他のアカデミア入門』明石書店、2023年