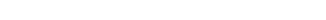解説記事
スマート農業が拓く、日本の農業の持続可能性(後編)
Date: 2025.10.01 WED
#初学者
#自然資本
#気候変動
環境負荷の小さい農業と儲かる農業の両立——SDGsへの貢献と経済的持続性
前編ではスマート農業による効率化や技術伝承の効果を解説しました。後編ではスマート農業が環境や社会に与える影響に焦点を当てます。
スマート農業の導入により環境負荷の低減を実現する手法を見ていきましょう。
ドローンや衛星画像を活用して広大な圃場の生育状況や養分状態を詳細にモニタリングします。
これらのデータをAIによって解析し、農作物の成長段階や土壌の状況に応じた、場所ごとの最適施肥量を導き出します。これにより、必要な場所に、必要な量をピンポイントに供給することが可能になります。土壌や地下水への肥料成分の余分な流出を抑え、環境負荷を大幅に低減できるのです。
病害虫や雑草対策においても、スマート農業は環境負荷低減に大きく貢献します。
ドローンを低空飛行させて撮影したカメラ画像をAIで解析し、病気の発生箇所や雑草の生育箇所を特定します。その情報に基づき、ドローンが農薬や除草剤を必要な場所にだけピンポイントで散布します。これにより、圃場全体に一律に農薬を散布する必要がなくなり、使用量を劇的に削減できるため、生態系への影響を最小限に抑えることができます。
ここでポイントとなるのが、スマート農業の活用により、環境負荷の低減と収益性の向上という、これまでトレードオフの関係にあり得た2つの要素を両立できる点です。資材の無駄を削減することが、環境負荷低減とコスト削減の双方に効果を発揮するというわけです。
前述の可変施肥やピンポイント防除は、環境負荷低減と同時に、資材費の低減という経済的メリットももたらします。肥料や農薬の無駄な使用をなくすことで、生産コストを大幅に削減できるのです。
国際的な資材価格の高騰や円安の影響は、農業者の営農コスト上昇に直結しており、このような“一石二鳥”の仕組みへの関心が急速に高まっています。
図1 スマート農業を駆使したサステナブルで儲かる農業 図作成:三輪泰史
環境価値の見える化がスマート農業の追い風に
今後このようなスマート農業をスピーディーに普及させていくには、環境に配慮した農産物が高く売れる状況を確保することが必須となります。消費者の「食」に対する意識が高まる中で、環境に配慮した農業は価値の高いものとの認識はひろがっています。日本総合研究所の調査でも、環境配慮等の社会課題に配慮した食には、現在よりもさらに1兆円程度の追加的な市場ポテンシャルがあることが示されています。
図2 「社会課題に配慮した食」の付加価値 出所:日本総合研究所
一方で、残念ながらその価値に対してプラスアルファの金額を支払おうという機運は高いとは言えません。いまは多くの消費者が、“環境に良い農産物は素晴らしいが、高いお金を出してまで買いたいわけではない”という状態と言えます。このようなギャップの解消に向け、官民双方でさまざまな取り組みが展開されています。
例えば農林水産省では、温室効果ガスを削減した農産物や、生物多様性保全に配慮した農産物の表示制度を設け、環境面での価値を消費者へ訴求し、適正な購入価格につなげる実証を行っています。
“環境への負荷が小さい=儲かる”となれば、農業者にとってスマート農業を導入するモチベーションとなります。言い換えれば、消費者の購買行動によりスマート農業を普及することが可能なわけです。
スマート農業でサステナブルで儲かる農業へ
食料・農業・農村基本法の改正が示すように、日本の農業は変革の時を迎えています。
農業者、研究者、企業、政府、そして消費者が一体となって取り組み、スマート農業によって「環境負荷が小さく、効率的で、魅力的な農業」の実現を目指すこと、それが今後の国内農業の目指す方向性と考えます。
これからは、スマート農業は単なる目新しい先端技術ではなく、私たちの豊かな食を支える基盤となっていくと言っても過言ではありません。