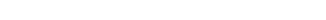イベントレポート
少子化の原因をZ世代と共に考える
Date: 2025.11.05 WED
#ソーシャル
#初学者
パネルディスカッションの風景。右からSMFGの岡本めぐみ、広告プロデューサーの落葉えりか氏、つむぱぱ社の安田舜氏、そだてるはたらくプロジェクト代表の河西歩果氏、モデレータを務めたロフトワークの奥田蓉子氏。会場内のプロジェクターで、リモート参加した南デンマーク大学人口学センター 助教の茂木良平氏とつないでトークを行った
2025年7月29日、GGPはロフトワークと共同でトークイベント『人口学者・社会起業家と問い直す: Z世代と共に向き合う、少子化時代の未来デザイン ~ReDesign Family & Work~』を開催しました。
世界の人口動態を分析する人口学者で少子化研究者の茂木良平氏、「そだてるはたらくプロジェクト」 を実践する社会起業家の河西歩果氏をゲストに迎え、少子化に陥っている社会背景や課題について分析いただきました。
後半のパネルディスカッションでは、今後の親世代そして働く世代の中心となっていく「Z世代」の視点から見た社会のありたい姿に着目。
三井住友フィナンシャルグループの岡本めぐみとZ世代である広告プロデューサーの落葉えりか氏、つむぱぱ社の安田舜氏とが加わり、議論を深めました。モデレーターはロフトワークの奥田蓉子氏が務めました。
理想の子ども数を実現できる社会に向けて
少子化研究者の茂木良平氏は、「日本の少子化の現状 企業や個人はどう考えるべきか」と題して講演。
日本の少子化の原因は未婚化・晩婚化
スペインよりリモート参加の茂木氏
茂木氏は少子化が改善すべき課題である理由を「希望するライフコースを歩めない人が増えていること」と指摘し、出生率低下の最大の原因は未婚化・晩婚化であると分析しました。
未婚化は結婚したくない人が増えたことを意味するのではありません。茂木氏の調査によると18~35歳の未婚者のうち84%は結婚を希望しているにも関わらず、未婚者の70%以上の人は交際相手がいません。経済状況を理由に交際できない人の実態があることを茂木氏は訴えます。
出所:茂木良平、樫田光、木村剛継(2024)数字で簡単にわかるニッポンの少子化問題
また、理想の子ども数を調査したところ未婚・既婚に関わらず平均は約2人であるのに対して、合計特殊出生率は1.15。多くの人が結婚や子どものいる生活を希望しているのに未婚に留まり、また希望する子ども数を多くの人が実現できてない状況であることを紹介しました。この理想と現実のギャップが少子化が社会課題たるゆえんであり、このギャップを生み出している要因をサポートするのが少子化課題だと説明しました。
理想の子どもを実現している人の割合。理想の子ども数は0、1、2、3、4、5人以上から選択(2024年、福井県「子育て意識調査」)より。出所:茂木良平
44歳以上の女性における無子割合。諸外国に比べ日本がダントツの1位 データソース:Human Fertility Database 作成:茂木良平
茂木氏は、人口を維持できる合計特殊出生率2.1を日本では半世紀もの間下回り続けた事実を突きつけます。
データソース:Human Fertility Database and Japanese Vital Statistics 作成:茂木良平
「奇跡的に出生率が回復しても、人口減少がおさまるのは60〜70年後。人口減少問題と少子化問題は分けて考えるべきです。でも、何もしないと人口は減り続けます」(茂木氏)。
データソース:人口統計資料集と将来人口推計 作成:茂木良平
こうした中、政府による少子化対策費は、2013年に3.3兆円だったのが2022年には6.1兆円に倍増し、経済的な支援は進んでいます。
しかし、その99%が子育て支援に充てられています。「少子化の要因の7割が未婚化・晩婚化という結婚行動、3割が出産行動にあることを踏まえると、予算の配分が逆転している」という事実を茂木氏は示しました。
働き方や家事分担は理想と乖離
では、希望の子ども数を実現するためにハードルとなっている要素は何なのでしょうか。茂木氏は労働環境や男女の家事分担についての課題を指摘しました。
まずは男性の長時間労働と週末労働です。佐賀市で行ったアンケートによると子どものいる男性の労働時間は9時間以上が約6割で、女性は1割。それに比べて、子どものいない男女では約3〜4割です。また子どものいる男性の2.5割が週末労働をしています。このことから、子どものいる家庭では、男性が仕事をし、女性が家事育児を担っている現状が浮かび上がります。
2024年佐賀市「結婚・出産・子育ての意向に関する市民アンケート調査」 出所:茂木良平
データソース:厚生労働省「雇用均等機会調査」 作成:茂木良平
その証左として、男女の家事・育児分担の理想は50:50でありながらも、実際には女性に偏っているという茂木氏の調査があります。男性の育児休業取得率は2023年時点で30%で、女性の84%の半分以下です。
育児休業や時短勤務労働など、国の制度を男性が利用しきれていない実態があります。
そして女性への家事負担が多いほど、第2子出産への意欲が低くなる傾向にあると言います。
出所:茂木良平、樫田光、木村剛継(2024)数字で簡単にわかるニッポンの少子化問題
男女の労働環境の公平化、出産後も女性のキャリアに不利益を与えない、非正規雇用などの的な不安要因を取り除く等、少子化対策として企業ができることはまだまだありそうです。
スペインのポンペウ・ファブラ大学、南デンマーク大学、国立社会保障・人口問題研究所など国内外のさまざまな機関で研究を行う茂木氏は、「研究だけに止まらず、少子化改善のためのアイデアを提案、実行していきたい」と、実践者としての立場も表明。NoteやXで、世界の少子化についての情報を発信中です。
(note: https://note.com/rmogimogi/ X: https://x.com/rmogi_jpn)
子育ては社会で行うという意識を醸成する
河西歩果氏
現在1歳と2歳の娘を育てながら働く河西歩果氏は、育児中の人が、柔軟な選択ができる社会を目指し「そだてるはたらくプロジェクト」を立ち上げ、育児と労働に関する研究や実験、実践の場づくりなどを行っています。
株式会社LouvyのCEOとしては、移動式・イベント特化型の託児サービス「SODAHATA」を展開しています。
フリーアナウンサーとして働く中で第1子を妊娠し、産休も育休もなく働いた経験から、共働き時代の育児をサポートし、社会で子どもを育てる価値観が定着していくことを目指しています。
河西氏は、仕事と育児の両立に希望がもてない原因を次の3つではないかと分析します。
1つ目は、就職活動時点での刷り込み。企業がアピールする「我が社は子育てしやすい環境ですよ」の言葉によって、両立が大変なものだという認識を学生に与えてしまう可能性があると指摘し、両立を頑張ることをポジティブに伝える必要性に触れました。
次に挙げたのは、社会システムの問題です。パートナー同士での育児分担や経済的な問題など、不安な要素が若い世代には多く、不安を解消できないと踏み切れないのではないかと言います。
そして最後に強調したのは、「子育て=ハンデ」という認識が社会に定着しているということです。会社側の「配慮」が子育て世代にとっては「機会損失」となっていたり、キャリアアップに影響を及ぼしている実情に言及しました。
図4点出所:そだてるはたらくプロジェクト
また、自身が出産時に陥ったジレンマについても「すぐにでも職場に復帰したい思いが強かった 。でも、目の前の可愛い赤ちゃんとももっと向き合いたいと思った」と明かしました。
このように、自身や周囲のリアルな感情をありのまま見つめてきた河西氏が、育児と働くことの両立を目指して発案したのが「そだてるはたらくプロジェクト」であり、託児サービスの「SODAHATA」です。
「SODAHATA」は、子育て中の人が社会から分断されずに、育児のリアルな様子を見せるというコンセプト。これは「社会で子育てをする」という感覚を醸成させることを目指したものです。
SODAHATAでは託児施設を別にするのではなく、イベント会場などの中で託児サービスを提供 出所:そだてるはたらくプロジェクト
これまでクリエイターズマーケットや企業のオフィス内に臨時託児ブースを設けるなど、子育て世代が働く場所で実施。
オフィスに1日限りで設置した託児ブースは、社内ニーズの調査にも役立ったと言います。
「共働きの子育て世代が7割の現代。労働環境の問題は、当事者だけでなく、社会全体が取り組むべき課題」と河西氏は締めくくりました。
社会に対する不安を抱くZ世代が見る子育てとは?
パネルディスカッション。右から、岡本、落葉氏、安田氏、河西氏、奥田氏。プロジェクターでリモート参加の茂木氏も参加
続いてゲストの茂木氏・河西氏に、Z世代の未婚でまだ子どものいないお二方を加え、パネルディスカッションを行いました。モデレータは、ロフトワークの奥田蓉子氏が務めました。
Z世代代表としての意見を述べたのは、つむぱぱ社の安田舜氏と広告プロデューサーの落葉えりか氏。
1999年生まれの安田氏が所属するつむぱぱ社は「親と子の幸せな時間を1秒でも増やす」をミッションとして子育て世代のためのコンテンツを制作している会社です。その事業内容の紹介と共に安田氏は、いずれ結婚や子育てをしたいとしつつも、入社3年目の現在ではまだ具体的な将来設計が見えていないことを語りました。
1997年生まれの落葉氏は、デンマーク留学の経験などからジェンダーやサステナビリティをメインテーマに扱う広告・コミュニケーションの会社を経て、現在はフリーランスとして自由な働き方をしていることを紹介しました。
トークのテーマは以下の3つです。
1. Z世代から聞く、理想の働き方とパートナーシップ
このテーマに対し、落葉氏は「私たちの世代は将来への不安が大きいのが特徴。先の参院選からも分かる通り、長く続くもの、大きな組織への信頼感が低く、だからこそ個人のスキルを磨くことを重視している」と同世代の多くに共通するスタンスと、自身のフリーランスとしての柔軟な働き方の関係を示しました。
それに対し河西氏は、理想の働き方を全て叶えられることはなくとも「常に自身の気持ちや状況を周囲に伝え、理解を求めることが肝要」と、自身の経験を語りました。
2. 「子育てもキャリアもあきらめたくない」という思いに、企業はどう応えるべきか
この問いかけに対して茂木氏は「日本では働くことへの意識が過剰ではないか」と指摘。海外で10年以上研究生活をしている経験から、ひとつの仮説を披露しました。
「キャリア志向と会社への帰属意識という軸で4象限を設定したら、日本は両方とも高い。例えば米国ではキャリア意識は高いけれど、会社への帰属意識が低い。そうした意識が、育児休業や時短勤務などをやりづらくしているのではないか。20代30代は育児に専念し、40代からのキャリアアップだってある」と。
その上で、仕事の流動性を高め、JOB型に転換していく社会の必要性を説きました。
安田氏は「Z世代の多様な価値観を周囲の大人が認めてくれているが、仕事で自己実現したい僕としては、もっと叱って欲しい(笑)。どんな存在でもよいと肯定されているからこそ、何者かにならないと社会で価値を認めてもらえないという不安の中で日々を過ごしている」と、漠然とした不安感が働き方への意識に繋がっている可能性を語りました。
一方で落葉氏は、「育児休暇だけが特別視されているが、留学などで長期間会社を休むなど休暇にも多様性があってよい。皆が様々な経験から新たな視点を得て戻ってくることが普通になる」と提案。
3. なぜポジティブな子育ての話が広がらないのか?
子育てのネガティブなイメージの分析を行っている河西氏は、自分にとっては「子育ては楽しく幸せなもの!」とし、「育児はキャリアになる」という見方を示しました。茂木氏は、講演でも示した通り女性に家事・育児が偏っていることを解消すべきとし、男性の働き方改善、行政支援の充実を求めました。
安田氏は、「子育ては大変だけれども、その先にある幸せや、子どもの愛おしさを、取り繕わず発信していきたい」と語りました。
パネルディスカッションでの議論を経て、GGP事務局の岡本は「柔軟で流動的な働き方が、社会を強くすると感じた。迷惑をかけてはいけないという思いに縛られがちだが、人間誰しも挑戦と失敗をして他者に迷惑をかけ成長している。迷惑と引き換えのポジティブな面に着目する寛容さが社会をより良くするかもしれない。」とZ世代との対話からの気づきを語りました。
(2025年7月29日 ロフトワークにて、文:有岡三惠/Studio SETO 写真:ロフトワーク)
アーカイブ
動画再生時間:約129分
00:02:42 GGP紹介
00:09:50 イベント本編開始