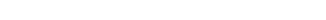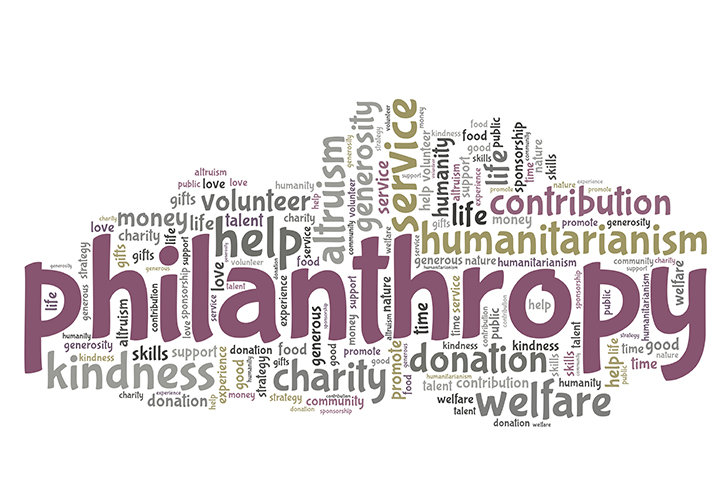インタビュー
少子化に向き合う社会デザインと実装に挑む
Date: 2025.11.21 FRI
#ソーシャル
#新規事業
SMFGで「少子化」の課題に取り組む岡本めぐみ 写真:ロフトワーク
GGPは2025年度、社会的課題に対して実践的に行動するプロジェクトを2つ立ち上げました。
重点課題として取り組んでいるのは「少子化」と「食と農」です。
「少子化」に関わるプロジェクトを率いるSMFGの岡本めぐみが、プロジェクトの目的とその先に描く社会的価値について語りました。
少子化はすべての人に関わる、みんなの課題
——プロジェクトとして重点的に取り組む課題として「少子化」を掲げた理由は?
岡本めぐみ 少子化は2つの側面で大きな課題だと考えています。
1つ目の側面は、経済成長や社会の持続性という国民全体への影響です。人口減少は、日本経済の成長が鈍化する要因になります。
また、少子高齢化で人口ピラミッドが騎馬戦型から肩車型へ変化していくと、若い世代の負担が増したり、国の財政が悪化するという問題も生じます。
「少子高齢化」を解決するのは国の仕事だと認識されがちです。
しかし、この社会課題を生み出している「社会」とは、結局は私たち1人1人、そして1社1社の集合体でしかありません。国だけでは変えられない。誰もが当事者であり、当事者だからこそ出来ることやすべきことがあるのではと思っています。
同時に、個人や1社だけでは解決できない壮大な課題です。
そのため、様々な企業や自治体、団体と一緒に課題の解決策を考えていく取り組みとして、「社会変革を実現するコミュニティ」であるGGPで、実践的なプロジェクトを立ち上げました。
国立社会保障・人口問題研究所ホームページ
——少子高齢化は日本経済や財政に対して具体的にどのような影響を及ぼしているのでしょうか。
岡本 私たちへの影響は、国の財政を見るとよく分かります。医療・介護・年金などの社会保障給付の財源は、社会保険料と公費が充てられます。社会保障費の公費負担は、今や国の一般会計の3割以上、最も多くを占め、年々増加していきます。
一方で税収はバブル崩壊以降低迷が続き、近年は伸びているとは言え、歳出の増加をカバーしきれていません。足りない分は国債に依存して負担を将来に先送りしています。
出所:財務省「これからの日本のために財政を考える」2025年4月
こうして毎年何十兆円もの赤字国債発行が続き、債務残高は日本のGDPの2倍を超えています。GDP対比の債務水準を諸外国と比べると、日本はダントツで世界1位です。
財政悪化により、もし日本の国債や通貨への不安が高まると、円安がさらに進行したり、物価や金利が一気に上がったりして、経済や私たちの生活が混乱するリスクがあります。
全く持続可能ではないこの状況を知ったとき私は大きな衝撃を受けました。
出所:財務省「これからの日本のために財政を考える」2025年4月
しかし、高齢化からは逃げられませんし、多くの人が長生きできるのは喜ばしいことです。高齢化を支えられる豊かな経済・社会を作るとともに、少子化がこれ以上進まないようにするしかありません。
人口が減るからGDPが下がっても仕方ないという考え方もありますが、GDPが成長せず、社会保障費だけが増えると、支え手の負担感が増してしまいます。
子どもを持たない選択をしている方や、既に子育てを終えた方、そして企業にとっても無関係ではない話です。
少子高齢化や人口減少が経済・財政に及ぼす影響は実に大きく、みんなに関係することなので、より多くの人と一緒に真剣に向き合いたいと思っています。
多くの人・企業が自分ごととして「少子高齢化」を考えるきっかけを、GGPのプロジェクトとして発信したいと思っています。
少子化原因の分析、子育て環境の改善、そして希望がもてる社会に向けて
——少子化改善のプロジェクトの先には、どのような展望があるのでしょうか。
岡本 前段では、全ての人に関わる社会課題であるとお話しましたが、だからといって社会のために子どもを持とうと考える方はあまりいないと思います。それは個人の人生における大事な選択です。
少子化の2つ目の側面である本当の問題は、「何らかの要因」によって、子どもを持つこと自体に希望を持てない状況や、子どもを希望しているのに持てない状況など、個々人の希望が抑制されてしまっていることにあります。
そこで、なぜ子どもを産み育てづらい状況なのかを考え、対処法を見出したいと思っています。
それには国が担う役割もありますが、企業や市民レベルで改善しなくてはいけないことも多いと考えています。
例えば、育児中に職場での時短勤務に負い目を感じたり、ベビーカーで電車に乗るのをためらったりという声をSNSやネット上ではよく見ます。
そうした分断を見た若い方が、「子育ては大変そう、自分には無理」と希望を失うことがあると聞きます。また、子どもが欲しくても雇用・所得の問題で諦める方も多いという調査もあります。
GGPでは、「子どもを持つことに希望がもてる社会、子どもを望んでいる人の希望が叶う社会」を目標として、実践的なプロジェクト「少子化に向き合う社会デザイン会議」を進めています。
企業やNPO、地方自治体と共に少子化が進む要因のリサーチやソリューションの検討を行い、実証実験や社会実装に繋げていくことを目指しています。
——プロジェクトの進捗状況を教えてください。
岡本 2025年度の6月から、連携パートナーのロフトワークとプロジェクトを始動しました。
まずは様々な要因が絡み合う複雑な少子化の課題構造を理解するために、システム思考を用いて因果関係を分析し、どのポイントを解決するべきかを検討するためにループ図を作成しました。
少子化の課題構造を分析したループ図
その後、8月には子育て関係の施設や地域活動の見学やインタビューを通じて、現場での取組や課題について学ばせて頂き、9月には解決するポイントの絞り込みや解決策の検討を行いました。そして、実証実験も念頭に置いた活動に入っています。
社会実装に向けて、実験の評価や反省をまとめてGGPで発信し、社会の財産として共有することを今年度は目指します。
実際に社会的インパクトを出すためのステップを踏んでみようと思っています。
——子どもを持つことに希望が持てること。そして子どもを望んでいる人の希望が叶うことが前提とのことですが、これまでのリサーチを経て見えてきた解決策の方向性など、思い描いていることを教えてください。
まずは子どもを持つことに希望を持てるためには、Z世代を中心にこれから親になる人たちにアプローチしたいと考え、Z世代の価値観や社会観に寄り添ったリサーチをしました。
Z世代らしい特徴の中にも、実は他の世代の人も潜在的に持っているものがあると思います。そこに焦点を当てたアイデアが、プロジェクトの中から出てくることに期待しています。
具体的な解決ポイントはまだ模索中ですが、今挑戦してみたいことのひとつは、子育て中の人と、そうでない人とが、一人の人として一緒に楽しめるコミュニティを全国に展開すること。それは、見学した活動からヒントを得て、私自身が感じたことです。
そして、子どもを希望する人の願いを叶えることも大切です。
すでに子どもがいる人でも希望の子どもの数を諦めてしまうケースもあります。経済的理由や、仕事との両立などで諦める、そういう阻害要因を取り除きたいです。
まず経済的な問題を考えてみると、望まない非正規雇用の問題。それを改善するためには、経済界がやるべきことは多いと考えた方が良いですよね。
そして教育費の問題もあります。過当競争によって教育費がどんどんと膨らんでいると言われます。
でも本質的な学びというのは実はお金をかけなくてもできるかもしれません。公教育でそれが担保できれば、様々な課題解決に寄与するでしょう。
さらに、今後共働きが増えて行くことを想定すると、そこから出てくるニーズをビジネスにすることも考えられます。
また、政策提言と組み合せた取組などもありえます。
たとえば少子化問題の改善のために世の中のお金の動きを変えるような仕組み。少子化対策のお金の流れは、子育て支援に対する税金の流れが主流なので、税金ではお金が回っていないところに、民間から資金が動いていく仕組みができたらいいなと思います。
本当にたくさんの要因が絡み合っているので、今年度のプロジェクトの中でどこまで検討できるかは分かりませんが…。
——今後のプロジェクトとして成長させるために、どのような企業、団体、人とコラボレーションをしていきたいですか?
少子化に関しては、結婚観や家族観、働き方や娯楽の広がり、他者との関わり方の変化など様々な個人的・社会的要因が複雑に絡み合っています。
それらの相関関係を、ループ図を用いて可視化して理解を深めることで、レバレッジポイントが見つかれば、多重的に解決できることがある手応えはあります。それでも、どれか1つの解決策では全部は解決しきれません。先程挙げたような観点について一緒に考えて頂ける方と是非お話したいです。
プロジェクトメンバーはそれぞれの立場が異なるので関心や見えるところが違います。それが多くの人と一緒にプロジェクトを進めている良さです。
今年度のメンバーは子育てに関わる企業・団体の方々が多いですが、もっと幅広く多くの方々の話をお伺いしたいと感じています。
子どもと全然関係ない業界の方でも、みんなが当事者だと思いますので、関心をお持ちいただけると嬉しいです。
(2025年9月8日、三井住友銀行本館にて)
岡本めぐみ
三井住友フィナンシャルグループ兼三井住友銀行 社会的価値創造推進部 事業開発グループ 上席部長代理
2009年に三井住友銀行入行。兵庫県での法人営業、事務システムの企画業務等を経て、2021年に財務省へ出向。現在はGreen Globe Partnersの運営や産学連携関連事業、社内外向けコミュニケーションの取組みに従事。
参加企業リスト(2025年10月末日時点/順不同)
・株式会社ロフトワーク
・認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
・KODOMOLOGY株式会社
・NPO法人放課後NPOアフタースクール
・株式会社ママスキー
・サイボウズ株式会社(ソーシャルデザインラボ)
・生駒市子育て健康部こども政策課
・株式会社赤ちゃん本舗(サステナビリティ推進部)