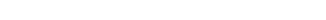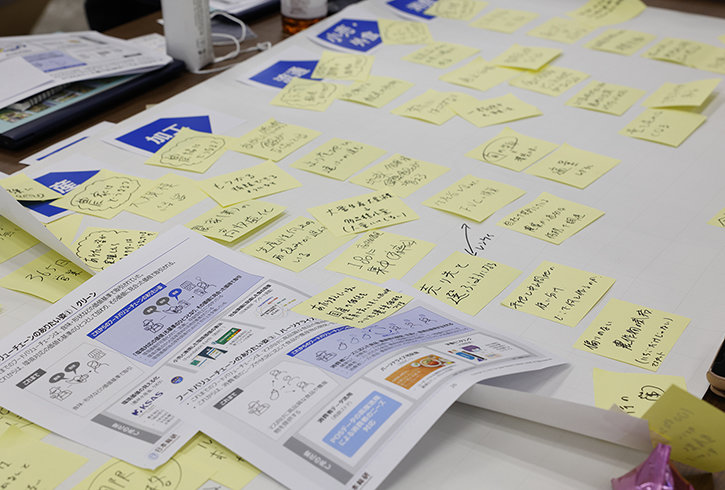インタビュー
マウンテンバイクからはじめる中山間地の新しい価値——ヤマハ発動機
Date: 2025.08.04 MON
#新規事業
#地域共創
#自然資本
ヤマハ発動機技術・研究本部の共創・新ビジネス開発部企画グループでMountain Ride Hubの事業に取り組む石田翔平氏(右)と前田帆乃夏氏(左)
GGP Edge Programとは?
| GGP Edge Program(以下Edge Program)は、本業を通じて社会的価値を創出する企業や事業をSMBCグループが支援するプログラムです。2024年度は7月より支援先を公募し、11月の選考会(詳しくはこちら)を経て3社を選出しました。 選出企業には、Edge Programとして、日本総合研究所の有識者によるメンタリングを3回、アントレプレナーシップや経営戦略を専門とする京都大学の山田仁一郎教授によるメンタリングを2回行いました。 本記事では、Edge Programに参加した各社の皆さまにプログラムの手応えを伺い、3回シリーズでレポートします。 |
参加企業:ヤマハ発動機
|
マウンテンバイク(以下MTB)を使って、地域をより豊かにする——。 |
“山を楽しむ”社会的価値をロジックモデルで言語化
——なぜ、「Mountain Ride Hub」という事業を始めたのでしょうか?
石田翔平氏
石田 きっかけは、MTB好きの社員たちが自分たちのためにつくったMTBのパークです。それが、静岡県周智郡森町というところにあるMillion Petal Bike Park(ミリオンペタルバイクパーク/以下ミリペタ)です。
自分たちだけで使っているのがもったいないと感じ、一般の人も使えるフィールドとし、社員が副業として運営をしていました。掛川駅から車で1時間もかかる山奥なのに、このMTBフィールドには年間2000人ほどの来場者がありました。
このミリペタの経験から、僕たちのチームリーダーである小倉幸太郎が山を利活用する可能性に気づいたんですね。山の新しい使い方の提案が他の場所でも展開できるのではないかと。それで、全国の使われていない里山をMTBで遊べる場所に変えていく構想が生まれました。それを社内の新規事業プログラムで提案したところ企画が通り、2023年からスタートしました。現在は10名のチームで事業開発をしている最中です。
——事業内容について教えてください。
石田 まずはMTBのフィールドをどうやって増やしていくか。そしてフィールドができた後に、どのように集客し、その場所の社会的価値を高めていけるか、という2つのフェーズがあります。 フィールドを作るところでは、「どういうものを作れば人が来てくれるのか」という企画構想から地域事業者や自治体と一緒に考えます。
同時に運営についても、来場客数を増やすための仕組みづくりを考えています。
例を挙げるとMTBスクールのカリキュラムを提供したり、車両の少ないところにはMTBをリースしたり、ITツールを導入して来客者を分析してリピート率を上げるなどです。環境づくりとサービスをパッケージにして提供するビジネスです。ヤマハのブランドを掲げることで安心してご利用頂けるフィールドをつくり、フランチャイズ展開することを考えています。
また弊社は海外顧客も多いため、ヤマハの商材を利用したアクティビティと地域資源を活用したインバウンド向けのアドベンチャートラベルの企画や誘客でも事業の仕組みづくりにチャレンジしています。
——Edge Programに応募した理由を教えてください。
石田 新規事業では、売り上げや収益がもちろん求められます。でもMountain Ride Hubにはそれだけではない価値があると思っています。そこを積極的にアピールするためには、その価値を見える化し、幅広く世間やステークホルダーに示す必要がありました。
私たちは山を使わせていただく立場なので、自治体や地域の方々にとってどのようなメリットがあるのか、地域にとっての意義をきちんと話せるようにならなくてはいけません。その必要性を感じていたタイミングで、Edge Programのことを知り、応募させていただきました。
Edge Programにヤマハ発動機がエントリーした時のロジックモデル 図作成:ヤマハ発動機
——日本総合研究所によるメンタリングを通して得た気づきはありますか?
石田 経済的な価値と社会的な価値のバランスの取り方について、見える化できたことが私にとっては一番大きな成果でした。
メンタリングには10名のプロジェクトメンバー全員で参加させていただきました。ちょうど事業化のための売り上げ目標やKPIを掲げ、その優先度を整理しようとしていた時期にメンタリングをしていただきました。
ロジックモデルを作成し直していく中で、経済的価値を求めるためには優先度が低いところが、実は社会的価値が高いという矛盾点がいくつかあることが分かってきました。
経済価値と社会的価値のバランスについてチームで議論することで、何を大切にすべきかという意識を共有でき、最終的に見える化できたことが重要だったと思います。
前田帆乃夏氏
前田 私は、アウトカムの方からバックキャストで、インプット側を検証していく過程を経たことが印象深かったです。私たちが求めているアウトカムのためのインプットやステークホルダーについて、具体的に考えられていなかったことが見えてきました。チームの中でそうした気づきを共有できたと思います。
この事業で自治体にとって良いインパクトを与えたいという視点は最初からありましたが、「自治体側が嬉しいことは何か」とバックキャストで具体的に考えていくことで、賑わいの創出や関係人口を増やすなど、解像度が上がってきました。
そして地域資源の活用や新たな地域特産物の発掘が自治体の満足度につながるのではないかという話が出ました。
我々が共同研究を行っている産業技術総合研究所(産総研)との取り組みを地域資源の発掘につなげて考えることができました。
石田 バックキャストでは、小中学校と教育面で連携するアイデアも出ました。これは事業目線で考えるとすぐに売り上げが立つわけではなく長期的な話になります。でもMTBのフィールドをつくる意義として、やはり地域の人たちから求められる状態を作っていきたい。それをはっきりと意識するようになりました。
ミリペタを作っている時、地主のお孫さんにMTBで遊んでもらったら、それをきっかけに親密になれた経験があります。そうした地域の人との将来も見越した関係づくりを、いろいろな場所でしていきたいと思っています。
前田 自治体や森林組合の方々と協力体制を作っていく時に「なんとなく森にいいことがあります」ではなく、私たちがやりたいことと、ステークホルダーの皆さんへの影響やメリットをきちんとお伝えできる準備が整えられたのかな。
図作成:ヤマハ発動機
——ロジックモデルをつくるプロセスで、社内ではオンラインホワイトボードを使っていたそうですね。
前田 オンラインホワイトボードは、チームみんなで共同編集ができるので、アイデアを発散できました。プロジェクトの全体像を見渡すのに役立ったと思います。ロジックモデルでは、その全体の中から自治体や地域によりフォーカスを当てて整理できたと思います。
——全体像の中からロジックモデルにはどのように収斂させていったのでしょうか。
石田 「会社にとっての親和性」と「社会貢献度の高さ」、この2軸で整理をしていきました。その中で、優先順位の高さをみんなで議論しました。その結果、従来並べていた項目のほかに重要性が見出せたものがあります。地域でのスポーツ教育とか、グリーンツーリズムです。また、地域のステークホルダーとしては、林業関係者など山に関わる人をどう巻き込むのかなど、新たな検討事項として入ってきました。
——ロジックモデルは今後どのように活用していくのでしょうか。
石田 ロジックモデルを活用するためには、ここで言語化したことに対して僕たちがどのようにアクションを起こしていけるかが今後重要になってくると思います。そのアクションを起こすための、グループ内での方針がまずは整った段階だと言えます。
Edge Program終了後に作成したロジックモデル4点 図作成:ヤマハ発動機
No Dig, No Rideの精神で進化するMountain Ride Hub
ミリペタにて、MTBを楽しむ石田氏と前田氏
——選考委員の山田氏とのメンタリングでは法整備の話題も出ていました。今後はどのような課題があるのでしょうか?
石田 日本ではMTBの普及が全く進んでおらず、先進国のMTB人口と比べると1/100以下程度で極端に少ない状態です。
これはMTBで遊べる環境がほとんどないことが大きな要因の1つです。
その背景として、日本の山は相続などで土地が細分化されており、道を走る許可を取ることが非常に難しい状況があります。
また、山道の管理については、法律面の整備が十分ではありません。管理者が不在の場所も多く、フィールド整備にとって大きな課題となっています。
そんな中で、MTBには「No Dig, No Ride 」という走る人達が整備を担う文化があります。その文化も合わせて取り込んで、管理がされず荒廃している山道の再整備を私たちが担いつつ、地域住民や色々なステークホルダーの方々と共存利用できるように進めています。
また、山田氏からは、「国や行政にアプローチをする必要があるのではないか」「そのためにMTBに関わる事業者や有識者を交えたコンソーシアムのようなものを設立してもよいのではないか」というアドバイスもいただきました。
日本の国土は約7割が山林であるにも関わらず、ほとんど有効活用ができていない状況は非常に大きな社会課題です。
この同じ課題に対して様々な観点で、山の利活用を模索・取り組みをしている事業者・団体が多くいると考えております。
そのような方々と協力して、行政側への提言・積極的なアプローチを行ったり、コンソーシアムの立ち上げなども検討をしている状況です。
——貴社が製造するMTBを普及させるだけではなく、より多くの人を巻き込んだ社会的インパクトのある事業展開をしていくということですね。
石田 そうですね。新規事業としては、社会的な価値にもしっかりと還元していくことを重要視しています。
「モノからコトへ」の時代です。私たちはMountain Ride Hubをコト事業として立案し、より幅広い視点で、社会的なインパクトを生み出すサービスを構築したいと考えています。
今は、山梨県の古道を活用したMTB事業者に協力していただいて、私たちのサービス内容を仮説検証する環境づくりをしています。まずは地域への影響を観測する場所として活用し、ビジネスとしても成立するし地域にもよいインパクトを与えられるロールモデルをつくりたいと考えています。
——お2人がこの事業に関わるきっかけは何ですか? またこの事業の魅力を教えてください。
前田 私は新入社員の1年目でこのチームに配属され、まったくMTBについては知らずに参加することになりました。
実際にMTBのパークで遊んでみると楽しくて、すっかり好きになりました!
MTBの魅力は、自分自身で探求できるところです。最初は、ただ降りるだけでしたが、だんだんと技を取り入れたりできないかな、とか。MTBもMountain Ride Hubの仕事も、自分が成長していけるのが楽しいと感じています。
石田 私は、もともと電動アシスト自転車を使った中山間地域のツーリズムに関心あり、過去にその企画提案をしていたのがきっかけの1つでした。
日本の山々には、自然と共存してきた歴史や文化が沢山あります。それらは日本独自の重要な資産だと考えております。その価値をしっかりと見出して、海外からのインバウンドのお客さんも含めて大きな価値を提供できるサービスを作っていきたいです。
——今後、この事業で取り組みたいことや展望などを教えてください。
石田 シンプルに“山に来たら面白いよね”ということを大事にしたいと思っています。
そして、山での遊びを通して、自然との新しい関わり方・共存の仕方を私たちのコア・バリューとして提案していきたいです。
MTBには、山に行って何度もフィールドを走りたくなるという性質があります。そのため四季折々に山の中をMTBで走りながら、季節の変化を体感できます。その体感や実感を通して環境や自然の変化に気づいたり、興味をもったりできます。
それはMTBだけに限らず、山林を楽しむコンテンツには同様の効果があると考えているので、それを多くのステークホルダーの方々と見つけて、形にして、広めていきたいです。
私たちはモビリティメーカーとして、自然と共に楽しむ乗り物を作ってきました。
環境問題や社会問題がある中、私たち独自の観点で、いろいろな企業や人を巻き込んで、より魅力的な山林の楽しみ方を提供していきたいです。
例えば野生動物の観察ツアーとか、ジビエ料理とか、キノコのハンターとか……。いろいろなツーリズムや遊びの形が考えられるのではないでしょうか。
前田 日本各所にある里山を、「管理が大変な負の遺産」ではなく、「次世代に引き継ぎたいもの」に変えていけたらいいなと思っています。
ミリペタにて、石田氏と前田氏
Mountain Ride Hub:詳しくはこちらへ
(2025年3月19日、ミリオンペタルバイクパークにて 文:有岡三惠/Studio SETO 写真:村田和総)
●メンタリングの目的:エントリー事業のロジックモデルを整備する。それによって、エントリー事業・活動が⽣み出す社会的価値が本業へ統合される道筋を整理する。
●ロジックモデル整備のメリット:エントリー事業の推進に係るステークホルダー(顧客・取引先・協働先・従業員・⾦融機関等)への理解促進、合意形成の円滑化。
●メンタリングのゴール:エントリー事業が本業へ統合される道筋について共通認識を持つ。