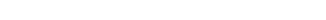イベントレポート
Sustainability Deep Dive Vol.3 文化人類学から自然を考える
Date: 2023.01.16 MON
#ソーシャル
昨今ではビジネスにおいても、人々の暮らしを構造化して捉える「文化人類学」の考え方やアプローチが注目されています。今回は京都大学人文科学研究所の石井美保氏と、自然と人間との共存のヒントを探っていきます。石井氏はインドやガーナでのフィールドワークを通して、人間が主体的に自然を変更するのとは異なる関わり方を研究し、自然の「開発」はもちろん「保護」という考え方にも潜む人間優位の関係を問い直しています。また著書やお話の中では、神霊とその力に満ちた「野生」とされる領域や自然との交わりやせめぎあいが豊かに描かれていて、そこには私たちが常識としている自然観を乗り越えるヒントも示唆されています。
イベントレポート
不可知な自然と人間の絡み合い
人間と自然が互いに働きかける場=野生
――石井さんは、自然と人間を単純に二分するのではなく、自然と人間の間で生まれ相互に働きかける領域を「野生」という言葉で説明されています。まずはそれについてご紹介頂けますか?
私の研究は、ヤーコプ・フォン・ユクスキュル[*1]とヴィクトーア・フォン・ヴァイツゼッカー[*2]の提唱した「環世界」の概念を手がかりにしています。それは、「一つの世界に多くの生物が適応している」という考え方ではなく、それぞれの生きものの生のあり方と相即するかたちで、それぞれにとっての世界が現れてくるという、相互的で複数的な世界の捉え方です。
この概念を参考にして人間にとっての「自然」を考えてみると、「自然環境」と「野生」という、異なるあり方が見えてきます。まず、「自然環境」とは、「自然」と「文化」の二分法に基づいて作られ、人間によって管理される環境であると言えます。自然保護区などが典型例ですね。それに対して「野生」とは、身のまわりの自然環境をも含めて、人間にとって不可知の領域を指します。それは人間が完全にはコントロールできない、危険に満ちた領域である一方、やりとりの相手としての環世界的な領域でもあります。
近代的開発に対する野生の力
私が調査したインド・カルナータカ州の南カナラの神霊祭祀では、憑坐(よりまし)に憑依(ひょうい)した神霊が村の領主に加護を与え、力を及ぼします。神霊とされるものは野生動物の霊をはじめ、人間にとって不可知の力なのですが、その力を呼び込むことで、村や水田に豊饒性がもたらされるとされています。
ところが2000年頃から大規模開発が始まり、森林の中に経済特区が建設されました。この経済特区の建設に伴い、住民が強制的に土地から退去させられたり、水源が干からびたりといった被害が続出し、開発への反対運動も起きています。その一環として、政府や企業との交渉やデモなどと並んで、「この土地を守りなさい」という神霊の託宣に基づく抵抗運動も行われています。また一方で、経済特区で人身事故が続いたこともあり、企業の幹部が主催者となって、神霊を慰撫するための儀礼が特区内で開催されました。また、工業プラントの中に神霊の社が建立され、祭祀が行われています。
経済特区の中で行われた儀礼 撮影:Deevaraaj Bhat
このように、大規模開発によって自然が破壊されていく一方で、危機を通じて神霊の体現する野生の力が感受され、特区の中に多元的な自然が現れるという事態が生じています。こうした状況は、「開発」対「自然」という二項対立よりも複雑な、人間と野生を含めた自然との関係を表していると言えます。
人間と自然の絶妙な関係
――野生と人間とのやりとりは一見非合理なことに見えますが、人間の暮らしと野生の間の適切な距離感・バランスが背景にあるのですね。
そうですね。野生の領域に棲む神霊とやりとりすることを通して、人間はさまざまな気づきを得られます。それは、自然との間に障壁を作るような関係とは違って、危険でもある野生の存在とあえて交渉し、相手との距離感を測りながら、絶えず関係を構築しなおしていくような関係です。
村の儀礼で授けられる神霊の託宣はいつも謎に満ちていて、さまざまな解釈が成り立つため、人々は託宣の意味を議論し、いつまでも問い直しつづけます。そうした神霊とのやりとりや、神霊をめぐる人々の絶えざる行為や論争の中で、村落社会の関係性が形成され、変化していくんです。
人間と野生を繋ぐ身体感覚のアクチュアリティ
――憑坐の発言が野生・神霊と繋がっている。そんな感覚が成り立つ基盤はどういうものでしょう?
それは、その土地の歴史性や日常的な関係性に加えて、儀礼の場での独特な音響や雰囲気などを含めた祭祀の全体が、人の身体に働きかける力によるものだと思いますね。南カナラでは、憑坐に神霊が憑依することは「ジョーガになる」と言われるのですが、それは不可視のものが目にみえる存在に「なる」という、移行的で遂行的な事態を指します。
――それは明晰な認識ではなく、儀礼で体感するものなのでしょう。石井さんの著書『環世界の人類学』[*3]でも木村敏の議論を参照しながら(「ある」ではなく)「いる」の話をされていますね。
私はそうした感覚を「アクチュアリティ」と呼んでいるのですが、それは安定的な「リアリティ」とは異なる、遂行的な現実感の生成を意味します。ただしそれは、往々にして制度化され、共有される安定的な「リアリティ」と相補的な関係にあるものでもあります。神霊を祭祀している南カナラの人たちも、近代法や経済制度によって支えられた現代世界を生きながら、同時に野生の領域とやりとりするというような、多元的な現実を生きているといえます。
自然の不可知さに触れる
――自然からの呼びかけを感じるアクチュアリティを、合理的に自然を管理しようとする近代社会のなかでどう捉えるか。その両義性がポイントなのですね。
東日本大震災後の東北地方で調査をしてきた友人によれば、彼の調査地で防潮堤の建設計画が進められた時、一部の漁師さんたちはそれに反対したそうです。彼らは、陸から海を見、海から陸を見ることで自分の位置や状況を確認し、判断している。防潮堤によって海と陸のかかわりが絶たれることの方が危険なわけですね。
南カナラの神霊も危険な存在ではあるけれど、村人たちは関係を絶たずにやりとりをする中で、より大きな災厄を逃れています。この地域では、神霊の憑依や託宣を通して、「マーヤ」と呼ばれる不可視の領域とやりとりし、そのメッセージを受けとることが重視されています。それは言い換えれば、人間の想定やリスク管理などを常に超えるような不確実性へと思いを致すことの大切さを示していると言えるかもしれません。
自然保護のもつジレンマ
トラ保護区における住民の排除
――ここまでは人間と自然が対立する中での野生との関係を伺いましたが、一方で自然保護区は、人間と自然の関係がより複雑に絡み合っているようですね。
インドにおいて、野生生物の保護は観光や国際評価といった点からも重要な政策のひとつとなっています。私が調査したカルナータカ州・北カナラの国立公園は、ゾウやトラなどの稀少動物が生息する昔からの自然保護区ですが、2008年にはトラ保護区に指定され、管理と保護がいっそう強化されました。そこでは科学的な頭数管理の下に、なるべく人間の影響を排除して自然を保護するという方法がとられています。
ですが、この地域には昔から「クンビ」と呼ばれる人々が、焼畑や狩猟採集を生業として暮らしていました。森はクンビの人々にとっての環世界です。新しく畑を開墾する時には祭祀が行われますし、野生のトラやコブラは神霊として祭祀されています。また、この地域がトラ保護区とされる以前は、儀礼的な集団狩猟は黙認されていました。集団狩猟では、獲物であるスイロクを初めに狩った人が次の村長とされたり、獲物を祖霊に捧げてから集落間で分け合ったりと、狩りと儀礼を通して森や精霊と共同体のかかわりが維持されていました。
トラ保護区内のクンビの集落 撮影:石井美保
ところが、この地域一帯がトラ保護区とされて、森林局による監視が強まったことで、クンビの人々の生活は危機に陥っています。彼らは、「自分たちこそが森を守ってきたのに、今や森から締め出されている」と嘆いています。政府が「自然」の範囲を決めて、自然保護の邪魔になる人間は周辺化される。環境保護が進むほど、地元の人と、その環世界との関係が危機に陥ってしまうという状況にあります。
自然保護による排除にどう抗するか
クンビの人々はこうした状況を打開するためにさまざまな試みをしていますが、そのひとつは2006年に施行された森林権法の活用です。これは指定部族をはじめ、伝統的に森に居住してきた集団の権利を保障しようとするものです。一部のクンビは、森への権利を得るために指定部族の地位を得ようとしていますが、それは一面では、近代的な人口管理のカテゴリーに包摂されることだといえるかもしれません。他方で彼らは、自分たちに不利益をもたらすような環境政策に対しては、デモや陳情といった活動も行っています。
さらにクンビの人々は、集団狩猟が禁止される中で、銃を使わずに伝統的な狩猟の「ふりをする」ことで、森での儀礼を存続させています。このようにクンビの人々は、さまざまな方法を駆使し、工夫を凝らして森との関係を維持しようとしています。
ケアを通した野生とのつながり
今日の発表の前半では、森林の中に経済特区が建設されることによって、地域の住民と神霊/野生との関係が危機に瀕しているという状況についてお話ししました。また後半では、特定の地域が自然保護区とされることで、森に生きてきた人々と森との親密な関係が阻害される状況をみてきました。これらの事例から、開発と自然保護とは一見対照的にみえながら、実はいずれも地域を境界づけ、分断し、ゾーニングすることで、その土地に生きるものたちを管理・統治し、操作しようとするという共通の特徴をもつことがみえてきます。
これに対して地域の人々は、法廷闘争やデモなどの手段で抗議する一方、儀礼や狩猟の実践を通して土地の神霊や精霊とかかわりつづけ、野生の領域——つまり自分たちの環世界との関係を維持しようとしています。
人間のつくりだした「自然環境」とは対照的に、野生の領域は人間が完全には管理できない不確実性と予測不可能性に満ちています。そうした「野生」は人にとって予測不可能だからこそ、互いにやりとりを続けていくことが必要なのですが、それは言い換えれば、相互的な「ケア」の関係だといえるかもしれません。そこでは人間と野生/環世界との絡まりあいや、ゾーニングでは区切れない生態系との長期的な関係性が重要になります。このように、自然と絶えずやりとりしつつ、適切な距離を保つという共生のあり方は、新型コロナウイルスの蔓延という近年の状況においても、重要な課題の一つとして浮かび上がってきたと思います。
合理性が見落としたケアへの視点
――開発と自然保護は違うように見えても、何を保護する/しないかの価値づけを人間の権力で決めてしまう点では同じで、ローカルな環世界は侵害されるということですね。そこに、クンビの自然人と近代市民的闘争のジレンマもあるように思います。
そうですね。そのどちらかとして自己を定位しないと、司法や行政による保護の対象と見なされず、開発への抗議も受け取ってもらえないという困難があります。ただ、そうした近代のアリーナからは外れた集団狩猟の儀礼が、実はクンビの人々にとっては、野生の領域と直接にやりとりする重要な機会になっているんです。
――自然人として保護されて近代的枠組に乗ることは、支援のための障害者の枠組が、そもそも健常者と障害者の区別を作るのと同じ構造のように思えます。
『不確実性の人類学』[*4]という本の中で、インドの人類学者のアルジュン・アパドゥライは、人に付随するリスクや信用度を量化した上で、それをそれぞれの人の「質」としてしまうという金融市場の仕組みを指摘しています。金融市場とは異なりますが、たとえば要介護認定などでも、スコアに応じた介護度が、その人の「属性」として実体化されてしまうといったことがあるのではと思います。クンビの人々と森との関係性にせよ、介護における人と人の関係性にせよ、現場でのケアの実践には、常に様々な不確実性が含みこまれています。そして、それにもかかわらず、そうしたものを数量化し、カテゴライズすることによって管理しようとする方法には、ある共通性がみられるように思います。それは「合理性のもつ非人間性」ともいえるのではないでしょうか。
(2022年6月3日オンラインにて 聞き手:山内 泰/大牟田未来共創センター 理事)
*1 ヤーコプ・フォン・ユクスキュル(1864-1944):エストニア出身のドイツの生物学者・哲学者。「その生物が周囲に与える意味の世界」すなわち「環世界」の概念を提唱し、その後の動物行動学や哲学、生命論に影響を及ぼした。
*2 ヴィクトーア・フォン・ヴァイツゼッカー(1886-1957):ドイツの医師・生理学者。自然科学的・生物学的になった当時の医学を批判的に捉え、医者と患者の共同関係に核心を据えた人間学的医学の基礎付けを試みた。
*3 2017年、京都大学学術出版会刊
*4 2020年、以文社刊
Profile
石井 美保 Miho Ishii
京都大学 人文科学研究所 准教授
宗教実践や環境運動をテーマに、アフリカのタンザニアとガーナ、南インドのマンガロールで人類学的フィールドワークを行う。主な研究テーマは憑依・呪術・儀礼をはじめとする人々の宗教実践で、これと関連して①村落社会における土地制度と母系制、②宗教実践と交易・商業との関係、③儀礼における身体性とパースペクティヴィティ、④神霊祭祀と環境運動、大規模開発の関係、⑤人間と非人間の社会的なインタラクション等のテーマについても調査研究を進める。主な著書に『環世界の人類学』(京都大学学術出版会)、『めぐりながれるものの人類学』(青土社)など。 第14回日本学術振興会賞受賞、第10回京都大学たちばな賞受賞。
アーカイブ
動画再生時間:約91分
00:00:08 GGP紹介
00:02:39 イベント本編開始