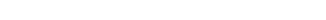イベントレポート
Sustainability Deep Dive Vol.4 分解から考える「サーキュラーエコノミー」を超えて
Date: 2023.03.29 WED
#ソーシャル
#自然資本
「サーキュラーエコノミー」が大きな注目を集めているように、自然の循環を踏まえたビジネスが求められています。では、そこで念頭に置かれる「循環」とは、一体どういうことでしょうか?今回は、「食と農」に関する歴史や思想の研究でさまざまなメディアから注目される京都大学人文科学研究所の藤原辰史氏をゲストに「根源的な自然の循環」を考えます。
イベントレポート
「分解」から見えてくる循環の世界
生産・消費・分解:根源的な循環
――藤原さんは「分解」というキーワードから、私たちが素朴に前提している経済や自然の捉え方を揺さぶる面白い議論を展開されています。最初にまず「分解」とは、どういうものでしょうか?
生物学のひとつに、いろいろな生き物の関係性を扱う生態学があります。全ての生態学がそうではないですが、基本的には次のような3者の循環を考えます。まず「生産者」で、これは太陽光を浴びて光合成を行い、二酸化炭素と水を吸収して、酸素とでんぷんを生み出す植物のことです。一方「消費者」は、植物が生み出したものを食べて排せつするなど、動物をイメージするとよいでしょう。そして枯れた植物や死んだ動物など生産と消費から生まれたものを細かく分解し、植物に必要な養分へ戻してくれるミミズやバクテリア、微生物など「分解者」がいます。こうした循環を考えると、「分解者」が非常に大きな役割を担っていることが分かります。
こうした循環の中で「分解」に人間はどう関わっているでしょうか? 例えば農業。作物を作るところが注目されがちですが、実際には土壌を作ることも重要です。そこでは腐敗した有機物を土の中に巻き込み、分解者たちに分解してもらい、その栄養分を使って植物が育つのを見守る。その点で農業は分解者と関わっています。私たちも日常的に、食事と排泄を通して分解者の一部を担っていますね。
――私たちは普段、「生産→消費→廃棄」という一直線で考え、その中で「廃棄物をどう少なくするか?」と考えがちですが、分解者という視点が入ることで、「生産・消費・分解」という根源的な循環が見えてきますね。
植物なしに人間は生きていけませんが、人間がいなくても植物は生きていけます。根源的な循環は、人間に先立ってあるわけですね。ですから「人間が循環をどうコントロールするか」ではなく「循環に人間はどうか関わっていけるか」という課題設定が重要なのです。人文学において人間をどうとらえ直すかは大きなテーマですが、こうした循環への関わり方から考えることができると思います。
分解における生成・創造
――藤原さんが「分解」に着目したきっかけは、どういうものだったのでしょうか?
大学院時代に、20世紀初頭に活躍したロシアの画家カジミール・マレーヴィチの研究をしている先輩がいました。「白の上の白」という抽象絵画を代表する作品が有名ですが、最初全く良さがわかりませんでした。でも発表を聞くに、マレーヴィチは、従来の絵画を解体しつつ、根源的な絵画にたどリついていったのだ、ということに、素人ながら心が動かされました。だから「白の上の白」では、抽象の極みでテクスチュア(絵の具の隆起)という物質性に行き着いたんですね。そんなラディカルさに感銘を受けると同時に、そこに農業と共通するものを感じたのです(笑)。
――単に壊すではなく、既存の何かを解体しつつ組み替えて新たに生み出しているところが「分解」のポイントですね。
「ほどく」という言葉は、ぎゅっと固まったものを解いたり、集中した富を施したり、というイメージです。読み解くもまた、本に凝固したものをほどく。昨今アンラーニングが注目されていますが、思想家の鶴見俊輔はそれを「学びほぐす」と言いました。生産と言われるものも「ほどく」の視点で見ると、ほぐした上で何らか別のかたちに整えなおし道筋をつけているように見えます。分解を通して、何かが生まれているんです。
完全性が前提される商品社会
――一方、私たちが普段考える生産と消費では、新品・完成品であることが当たり前となっています。藤原さんは著書でも、生産が新品・完成品を目指していることへの違和感を指摘していますね。
自分用にカスタマイズしたパソコンが一部の蛍光灯のみ壊れたことがありました。その際、自分で部品を買って修理して再び使うようにしたのですが、まるでパソコンの声が聞こえてくる思いでした(笑)。「壊れるモノを慈しむ」というモノへの考え方は、分解者的だと思います。
一方、現在の商品の生産体制では新品・完成品が前提なので、修理コストは高く、故障したら廃棄・交換が推奨されます。こうしたモノへの考え方は、実は人に対する考え方ともつながっていると感じます。私の学生たちの就職活動を見ていても、自らを画一的で完全な労働商品に仕立てるかのようです。でも私たちは誰もが、精神的身体的に完全ではないし、子どもやお年寄りなど年代によっても違いますよね。
――たしかに私たちの社会で、ほとんどの商品は完全さが前提で、欠陥品は不完全なものとして廃棄されます。その点「分解」は、そんな完全・不完全という二項対立を相対化しているように思います。
たしかに根源的な循環では、完全・不完全の構図はありませんね。私たちの社会は、根源的な循環とは異なり、「中枢-末端」のモデルに慣れてしまっているのでしょう。それは放射線のように一方向に流れるモデルです。だから「生産→消費→廃棄」の一方向モデルにおいて「どこをどうするか」と持続可能性や自然との関係を考えるのには強い違和感があります。循環モデルで考える必要がありますね。
循環経済(サーキュラーエコノミー)の外部
――循環モデルで考えるという点で、サーキュラーエコノミーの話に移りましょう。環境省の定義は次のようなものです。どのように見てらっしゃいますか?
サーキュラーエコノミーという概念はもともとEU発祥ですが、EU的なサーキュラーエコノミーの定義としては100点満点でしょう。でも、これでは地球規模の危機に立ち向かうのは難しいのです。本来はサステナブルも、「地球の自然環境の持続可能性」のために「経済を含む人間の営みがどう変わるか」という問いだったはずです。それがいつのまにか「経済の持続可能性」の話になってしまっているように感じます。
例えば「廃棄物の発生抑止」はたしかに大事です。しかしもっと原理的に捉え直すと、廃棄物は分解者たちの食べ物で循環を生み出す要素です。むしろ分解者たちが最大限活動できるように社会を整えていく上で、廃棄物のありかたを考えることが重要となります。
また循環の捉え方についても、ここでの循環は閉じたイメージで静的すぎるように思います。実際の循環は、太陽光という地球外からの一方向的なエネルギーを受けて、それを地球の外に出すことで成り立っているものです。
――循環のサークルを駆動する原理が、循環の外側にあるわけですね。ですが循環にとって不可欠な外部は、見えなくなりがちです。
外部が見えない点は資本主義もそうですね。資本主義を支える重要な外部の一つが「家族」です。経済を回すのに不可欠な労働力を家族は自発的に生み出します。それは情緒的・感情的・身体的・生殖的なセクシャリティの領域です。しかしこれまでの経済学は、家庭の領域を排除しないと経済を論じられなかった。そして閉じた体系としての「経済」の言葉を用いて経済を回す議論をしてきた。そのツケを今日私たちは支払っているのでしょう。ちなみに家政学はこの問題を扱うことを使命として19世紀に登場した学問です。
また、家族は歴史的に女性の領域と見なされ、無償化されていました。『アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か』(カトリーン・マルサル著)という世界的ベストセラーがあります。経済学の父スミスは、料理やケアを経済の議論から省いていると批判しています。そして夕食作っていたのは母だった、と。そして夕食の材料は自然からしか調達できません。もちろんスミスの思想はもっと複雑で、マルサルの論じ方には疑問もあるのですが、分解の哲学と経済学批判のつながりはマルサルの指摘した領域にあることは間違いありません。
私たちは、家族の中の自然性や自然環境の大事な部分を、「資源」という言い方で手段化してきたんですね。その在り方を根本的に捉え直す必要があります。だから生態学と経済学を結びつける新しい経済学の理論が求められていますし、自分もそれを目指しています。その問題意識からすると、この環境省の定義は人間中心主義的で、旧来の狭い経済学の議論に留まっていると思います。
「分解者」としての私たち
分解者的な人の営み
――微生物たちの分解の営みを、私たち人間の営みで捉えるとどんなイメージでしょうか?
ドイツの哲学者アルフレート・ゾーン=レーテルは、ナポリ人の営みに分解者を見いだしています。第一次大戦後のヨーロッパ、ナポリの街に滞在したゾーン=レーテルは、ナポリ人が完全で壊れないものを薄気味悪く感じる一方、壊れゆくものに寄り添い、修繕しながらケアして使い続ける技術を高く評価しました。
また私が住んでいた東京の公営住宅にゴミ拾いのおじさんがいました。ゴミ捨て場をすごく清潔に保ちながら、子どもたちのために段ボールでおもちゃをとても器用に作るのですね。子どもの誕生日に段ボールケーキを持ってきてくれたりして、子どもにも親にも人気でした。ゴミになるはずのものがおもちゃになって、人のつながりも生まれる。ナポリ人にしても、誰かが助けてくれることを前提に、壊れものを使っています。分解者は人をつなげているのです。
価値転換のきっかけとなる分解者
一方で、私たちは、歴史的・社会的に廃棄物を扱う人を経済や社会の外側に置き、差別してきました。差別や排除、家族と女性など、話が飛んでいるように感じられるかもしれませんが、分解の視点で見ればつながっています。
――従来の社会や経済の閉じた循環から排除された人の営みに、分解者が息づく根源的な循環へと価値転換するきっかけがあるんですね。
『分解の哲学』 図版提供:青土社
私たちが普段当たり前と思っている土俵そのものを捉え直したいのです。そうした価値転換への関心は高まっていると思います。拙著の『分解の哲学』(青土社、2019)の帯を書いてくださった坂本龍一さんは、自身の作品コンプリートボックス『2020S』で土に還るCDケースを採用しておられます。アパレル業界やデザイナー主催の会で「分解の哲学」の話をしたこともあります。コレクションに合わせて大量生産大量廃棄しているサイクルへの問題意識が、業界にはあるのですね。そこで「10年かけて服をつくる」とか「和服の見直し」とか、分解的な服のあり方も議論されました。また建築のコンペ「建築新人戦2021」で審査をした際、ある若手建築家が「腐っていく建築」を出してきました。
分解の感覚・感性
――クリエイティブな領域で分解的な感性が注目を集めている一方、私たちの日常はまだまだ狭いサイクルに閉じがちです。分解の感覚や感性を培うには、どうしたらよいでしょう?
ドイツの教育者フリードリヒ・フレーベルの積み木の話がヒントになります。フレーベルによれば、積み木は宇宙の摂理を表しています。積み木では、かたちを成そうと積み上げていき、完璧なかたちができたと思ったら、子どもがバーンと崩してしまう(笑)。そこでは同じ要素でさまざまなものが構成されては崩れ、また構成されるが繰り返されます。そうやって戯れることが重要だと言うんですね。私たち人間もまた、宇宙を循環している分子がたまたま集まったもの――生物学者福岡伸一さんの言葉では「分子の『淀み』」――として成り立っています。そんな摂理を体感できるのが積み木なのですね。
――積み木で「つくる」と「ほぐれる」の双方と戯れることで、完成品とか完全さへの感覚も変わってくる感じがします。
最近読んだ『皮膚、人間のすべてを語る――万能の臓器と巡る10章』(モンティ・ライマン著、塩﨑香織訳、みすず書房、2022)も面白かったです。それによれば、皮膚はミステリアスな世界です。でこぼこしていて、奥の方まで空気が入り、微生物が住み、免疫細胞も活躍している。皮膚は人間なのか、空気なのか、微生物なのか…。ある意味土壌と似ていて、皮膚に住む微生物が皮膚の破片と汗を食べてくれていて、糞をしている。それによって肌のうるおいが保たれています。個体を区別する輪郭は、実はぼけているんです。そんな現実を知るのもヒントになるかもしれません。
――私たちの身体がすでに、生産-消費-分解という根源的な循環に属しているということですね。
ただ一方で厳しい現実もあって、それは人間には葉緑素がなく、光合成によって二酸化炭素から酸素とデンプンを生み出せないということです。植物にもっと敬意を持つ必要がありますね。一方で私たち人間にできるのは、ちゃんと分解の一部を担うことです。そんな視点から、市場の循環モデルをもうちょっともみほぐして、柔らかく捉え直す哲学(論理構成の転換)が大事だと思います。
(2022年7月7日オンラインにて 聞き手:山内泰/大牟田未来共創センター理事)
Profile
藤原 辰史
京都大学 人文科学研究所 准教授
歴史学者。専門は農業史、食と農の思想、ドイツ現代史。主な著書に『ナチス・ドイツの有機農業』(第1回日本ドイツ学会奨励賞)、『カブラの冬』、『稲の大東亜共栄圏』、『ナチスのキッチン』(第1回河合隼雄学芸賞)、『食べること考えること 』、『トラクターの世界史』、『戦争と農業』、『給食の歴史』(第10回辻静雄食文化賞)、『食べるとはどういうことか』、『分解の哲学』(第41回 サントリー学芸賞)、『縁食論』、『農の原理の史的研究』がある。2019年2月には、第15回日本学術振興会賞受賞。
アーカイブ
動画再生時間:約90分
00:00:24 GGP紹介
00:02:53 イベント本編開始